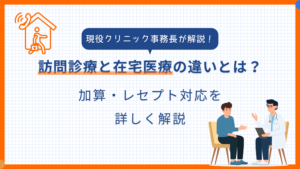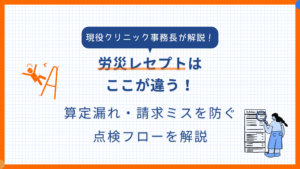訪問診療の「居宅」と「施設」の違いとは?算定とレセプトで押さえるべきポイント
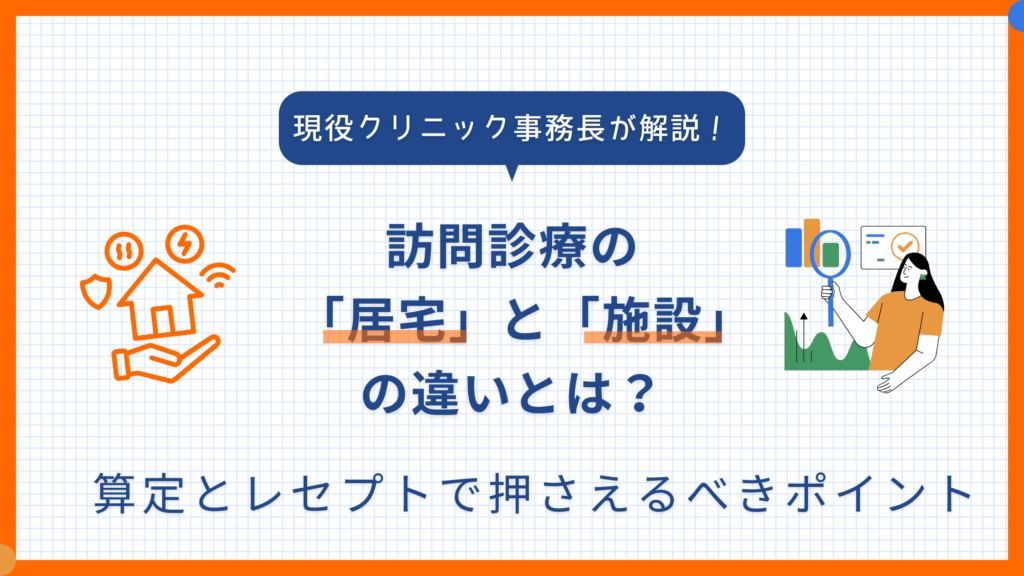
訪問診療を行う際、患者の生活場所が「居宅」か「施設」かによって、診療報酬の算定方法や減算ルールが大きく異なります。
この違いを正しく理解していないと、同一建物減算の未適用や加算漏れ、返戻といった問題につながり、クリニックの収益に直接影響します。
本記事では、
- 「居宅」と「施設」の違い
- レセプト算定で注意すべきポイント
- 返戻を防ぐための実務的な工夫
について詳しく解説し、訪問診療に強い請求体制を整える方法を紹介します。

株式会社パドルシップ 代表取締役
京都大学卒、京都大学大学院修了
総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。
江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。
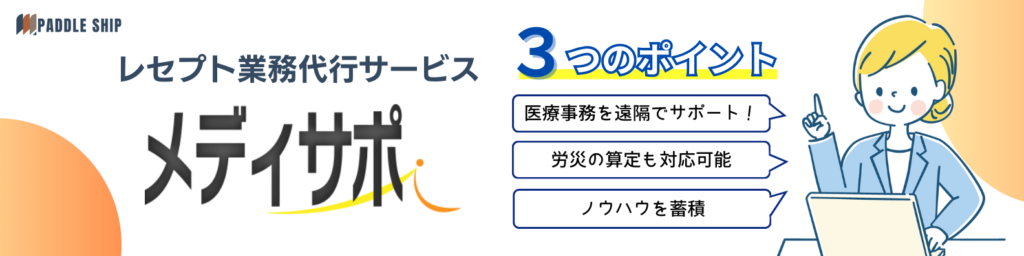
1. 訪問診療における「居宅」と「施設」の意味
訪問診療の診療報酬は、患者の生活場所によって大きく変わります。以下でそれぞれの特徴を押さえましょう。
居宅とは?
居宅は、患者が自宅や親族宅などで生活している場合を指します。
- 該当例:自宅、親族宅、個別賃貸住宅
- 特徴:訪問診療料に減算なし、在宅時医学総合管理料(在総管)の算定が可能
施設とは?
施設は、介護や生活支援を提供する集合住宅や高齢者施設を指します。
- 該当例:サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)、有料老人ホーム、グループホーム、特別養護老人ホームなど
- 特徴:同一建物内で複数の患者に訪問する場合、2人目以降は訪問診療料が減算(同一建物減算)
※どの住まいが施設に該当するかは、契約形態や提供サービスの有無で判断します。
介護施設の代表例と特徴
- サ高住:比較的自立した生活が可能な高齢者向け。外部サービス利用で生活支援を受ける。
- 有料老人ホーム:介護・食事・生活支援を一体的に提供。
- グループホーム:認知症高齢者を対象とした少人数共同生活型。
- 特養(特別養護老人ホーム):要介護3以上が原則。低所得者向けで費用負担は比較的軽い。
これらの施設は、同一建物に複数人が居住しているため、訪問診療料の減算対象となります。
2. 居宅と施設の違いがレセプト算定に与える影響
訪問診療では、「居宅」か「施設」かで以下の点が変わります。
- 訪問診療料:居宅→通常点数、施設→2人目以降減算
- 在総管(在宅時医学総合管理料):施設入居者も算定可能だが、条件や届出確認が必須
- 必要書類:施設の場合、契約書やサービス内容の確認が追加で必要
注意点
「居宅」なのに施設扱いで請求したり、その逆をすると、過大請求・返戻の原因になります。
3. よくある返戻原因と防止策
訪問診療の請求でトラブルが起きやすいのは次のケースです。
① 同一建物減算を適用しなかった
- 原因:施設に複数患者がいるのに1人目料金で請求
- 防止策:訪問予定時に「施設別患者リスト」を確認、レセプトソフトに同一建物設定を追加
② 居宅と施設の違いを理解していない
- 原因:サ高住やグループホームを「居宅」として扱ってしまう
- 防止策:契約内容・住所・サービス状況を訪問前に確認し、スタッフで共有
③ 書類不備
- 原因:在宅療養計画書や看護指示書の保存漏れ
- 防止策:書類は電子化してクラウドで管理、月次で必須書類の完備チェックを実施
④ 加算漏れ
- 原因:特別管理加算や在総管の請求忘れ
- 防止策:加算対象患者の一覧を運用、請求前にダブルチェック
4. 居宅と施設で異なる算定ルールまとめ
訪問診療では、患者の居住場所によって診療報酬点数や加算要件が異なります。以下では、居宅と施設での主な違いを詳しく解説します。
① 訪問診療料(基本点数)
- 居宅
- 患者宅への訪問診療は、基本点数をそのまま算定できます。
- 【例】在宅患者訪問診療料
- 月2回まで:830点(初回)+2回目以降410点
- 月2回まで:830点(初回)+2回目以降410点
- 減算なし。
- 患者宅への訪問診療は、基本点数をそのまま算定できます。
- 施設
- 同一建物内で複数の患者を診療する場合、2人目以降は逓減(半額など)。
- 【例】在宅患者訪問診療料
- 1人目:100%
- 2人目以降:50%(410点→205点)
- 1人目:100%
- サ高住・グループホーム・老人ホームなど、共同生活型は基本的に減算対象。
- 同一建物内で複数の患者を診療する場合、2人目以降は逓減(半額など)。
② 在宅時医学総合管理料(在総管)
- 居宅
- 条件を満たせば算定可能。
- 要件:訪問回数・医療計画書・同意書の作成。
- 条件を満たせば算定可能。
- 施設
- 算定可能だが、以下の追加要件に注意:
- 「在宅療養支援診療所(在支診)」の届出が必須
- 強化型在支診の場合、加算や評価が優遇
- 「在宅療養支援診療所(在支診)」の届出が必須
- 施設入居者でも、医師が総合的管理を行う場合は算定できる。
- 算定可能だが、以下の追加要件に注意:
③ 同一建物減算
- 適用対象
- サービス付き高齢者住宅(サ高住)
- グループホーム
- 有料老人ホーム
- 特養など
- サービス付き高齢者住宅(サ高住)
減算の基本ルール
- 1人目:通常点数
- 2人目以降:訪問診療料が半額
- 適用し忘れると過大請求→返戻リスク
④ 緊急時訪問加算・夜間・深夜加算
- 居宅・施設共通
- 緊急時の訪問は加算可能(在宅患者緊急時訪問加算)
- 夜間(18時~22時)、深夜(22時~6時)は別途加算あり
- 緊急時の訪問は加算可能(在宅患者緊急時訪問加算)
- 注意点
- 訪問時間を正確に記録することが必須(カルテ・レセプト整合性が重要)
- 訪問時間を正確に記録することが必須(カルテ・レセプト整合性が重要)
⑤ 特別管理加算
- 居宅
- CVポート管理、在宅酸素療法など、患者が高度な管理を必要とする場合に加算
- CVポート管理、在宅酸素療法など、患者が高度な管理を必要とする場合に加算
- 施設
- 算定可能だが、患者ごとの管理実績記録が必要
- 訪問時の観察内容や指導内容を明確にカルテ記載
- 算定可能だが、患者ごとの管理実績記録が必要
⑥ 届出要件と影響
- 居宅のみの場合
- 在宅療養支援診療所(在支診)の届出がなくても、基本的な訪問診療は可能
- 在宅療養支援診療所(在支診)の届出がなくても、基本的な訪問診療は可能
- 施設を含む場合
- 在支診の届出がないと、在総管や緊急時加算が請求できない
- 強化型在支診を届け出ていれば、ターミナルケア加算など評価が優遇
- 在支診の届出がないと、在総管や緊急時加算が請求できない
⑦ 必要書類
- 居宅
- 在宅療養計画書、訪問診療記録、同意書
- 在宅療養計画書、訪問診療記録、同意書
- 施設
- 上記に加え、施設との契約内容、介護サービス情報、カンファレンス記録
- 上記に加え、施設との契約内容、介護サービス情報、カンファレンス記録
以上をまとめると以下のような表になります。
| 項目 | 居宅 | 施設 |
| 訪問診療料 | 減算なし | 同一建物2人目以降は半額 |
| 在総管 | 算定可 | 算定可(在支診届出必須) |
| 同一建物減算 | 該当なし | サ高住・GH・有料老人ホーム等で適用 |
| 緊急時加算・夜間加算 | 訪問時間の記録必須 | 訪問時間の記録必須 |
| 特別管理加算 | 算定可 | 算定可(記録必須) |
| 届出 | 必須ではない | 在支診・強化型在支診の届出で加算有利 |
| 書類 | 訪問記録・計画書 | 計画書+施設契約情報・カンファレンス |
5. 訪問診療に強いレセプト体制を整えるには
訪問診療のレセプト業務は、外来診療と比べて圧倒的に複雑です。
理由は以下の通りです:
- 加算ルールが多く、頻繁に改定される
- 患者の居住場所(居宅 or 施設)で算定条件が変わる
- 同一建物減算など、入力時に誤りやすいルールがある
- 施設契約情報や訪問記録など、書類整合性が必須
このため、属人化やミスが発生しやすく、返戻や過誤請求による経営リスクが高くなります。
これを防ぐには、「ルールの見える化」「データ管理の一元化」「専門チェック体制」の3本柱で体制を構築することが重要です。
① 居宅・施設別の算定ルールを可視化する
訪問診療の請求精度を高める第一歩は、複雑な算定ルールを誰でも確認できる状態にすることです。
- やるべきこと
- 「居宅」「施設」の違いをまとめた早見表を作成
- 同一建物減算が適用される施設一覧を共有
- 訪問診療料・在総管・各種加算の要件一覧をルールブック化
- 「居宅」「施設」の違いをまとめた早見表を作成
- ポイント
- 紙資料より、Googleスプレッドシートや院内ポータルで管理し、常に最新版にアップデート
- 診療報酬改定時に即時反映
- 紙資料より、Googleスプレッドシートや院内ポータルで管理し、常に最新版にアップデート
② 情報管理を仕組み化する
属人化を防ぎ、ミスを減らすためには、情報を一元管理できる仕組みが必要です。
- 管理対象
- 患者ごとの居住場所(居宅 or 施設)
- 施設別の居住者リスト(同一建物減算対応)
- 加算対象患者リスト(特別管理加算・在総管など)
- 患者ごとの居住場所(居宅 or 施設)
- 実務の工夫
- 訪問スケジュールと請求データを連動(電子カルテ or Excel)
- 月初に「施設別患者一覧」を確認し、訪問予定と同期
- 加算対象患者はアラート機能で通知(レセプトソフトで設定可能)
- 訪問スケジュールと請求データを連動(電子カルテ or Excel)
③ 書類・記録の整合性を確保する
返戻の大きな原因は書類不備です。訪問診療は、在宅療養計画書・看護指示書・多職種カンファレンス記録など、確認書類が多いのが特徴。
- 対策
- 必要書類をPDF化してクラウド共有(Google Drive等)
- 月次で「書類完備率」をチェック
- 書類提出遅れを防ぐため、訪問直後の電子入力を徹底
- 必要書類をPDF化してクラウド共有(Google Drive等)
④ スタッフ教育と業務マニュアルを標準化
訪問診療レセプトは外来経験者でも対応が難しいため、明確な教育体制が必要です。
- 取り組み例
- OJT+動画マニュアルで短期間習得をサポート
- 「よくある返戻理由」と「防止策」をリスト化して共有
- 診療報酬改定情報を定期的にスタッフに周知
- OJT+動画マニュアルで短期間習得をサポート
⑤ 外部専門サービスの活用
人材不足や複雑な加算管理に悩む場合、レセプト代行・点検サービスの導入が有効です。
- メリット
- 採用コスト・教育コストが不要
- 診療報酬改定への対応を外部に任せられる
- 加算漏れや過誤請求を大幅に減らせる
- 採用コスト・教育コストが不要
- 当社サービス「メディサポ」なら
- 訪問診療特有の加算チェック・返戻防止
- 病名登録や施設別リスト管理を支援
- 15年以上経験のある専門スタッフによる点検で返戻率を低減、経営の安定化に直結
- 訪問診療特有の加算チェック・返戻防止
⑥ レセプト業務を“属人化”から“仕組み化”へ
最終的な目標は、誰か一人のスキルに依存しない体制を作ること。
- 情報は共有ツールに集約
- ルールはマニュアル化
- チェックは外部も活用
こうすることで、返戻ゼロを目指しながら、スタッフの負担を軽減し、診療に集中できる環境を実現できます。
まとめ|訪問診療レセプトの精度を高めるために
訪問診療において、「居宅」と「施設」の違いを正しく理解することは、診療報酬を安定的に確保するための重要なポイントです。
- 居宅:減算なし、在総管や加算の算定がしやすい
- 施設:同一建物減算あり、契約や書類管理が複雑
この区分を誤ると、返戻・過誤請求・算定漏れといった問題に直結し、経営リスクが高まります。
特に注意すべきは以下の3点です:
- 同一建物減算の適用漏れ防止(施設別患者リストの整備)
- 加算要件と届出の確認(在総管・特別管理加算・強化型在支診)
- 書類整合性の確保(計画書・指示書・カンファレンス記録)
さらに、複雑な加算管理や頻繁な報酬改定に対応するには、
- 算定ルールの見える化(早見表・マニュアル)
- 情報管理の仕組み化(訪問スケジュールと請求データの連動)
- 外部専門サービスの活用(プロによるレセプト点検で返戻防止)
これらを組み合わせることで、返戻ゼロを目指しながら、スタッフの負担を軽減し、診療に集中できる体制を構築できます。
メディサポでは、訪問診療に特化したレセプト支援を提供しています。
加算チェック、病名登録、返戻防止までトータルでサポートし、属人化のリスクを解消。
▶ 訪問診療レセプトの仕組み化・精度向上なら → メディサポに相談する
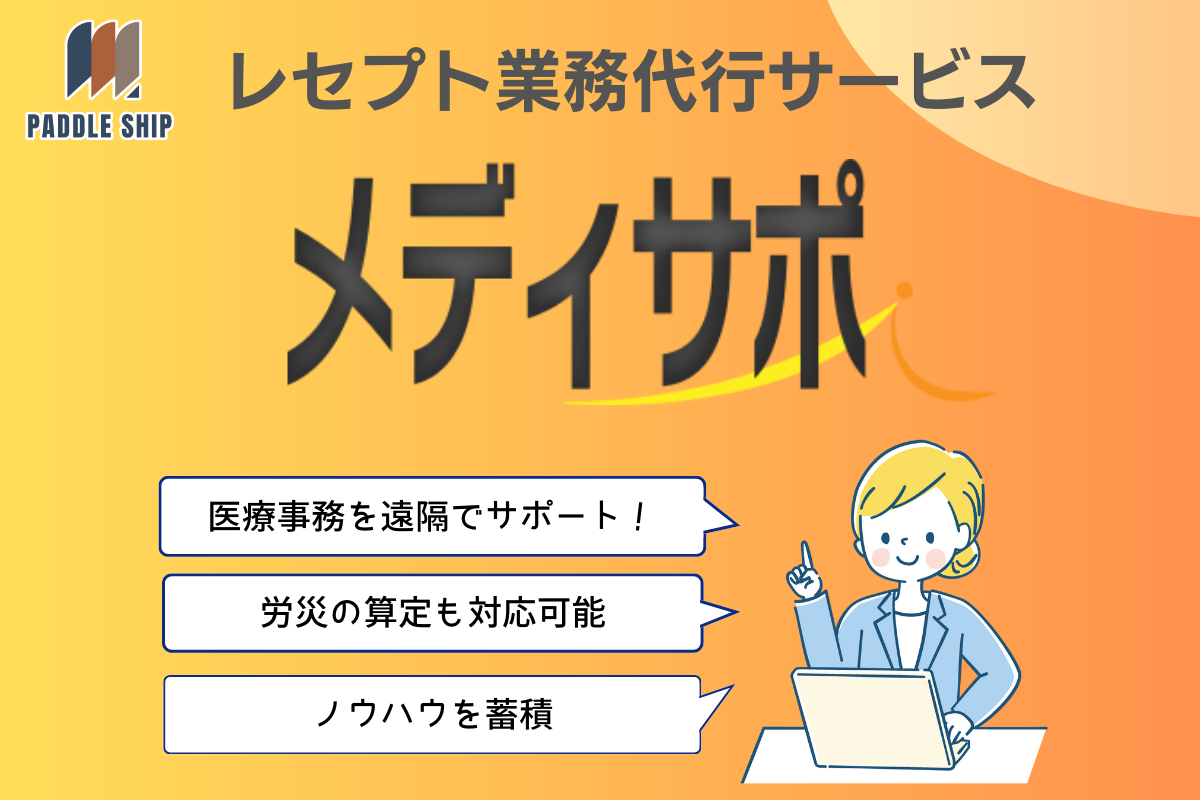
医療事務の人材採用・育成の負担を解消
「レセプト業務代行」
電子カルテデータより集患や運用の課題を抽出
クリニック事務長が作った経営分析ツール
「メディカルボード」
電子カルテデータより集患や運用の課題を抽出
- データ処理の煩雑さ/工数の増大
- 分析の切り口がわからない
現場でのこのような課題を解決するために、
電子カルテのデータを瞬時に見える化するツールを開発しました。