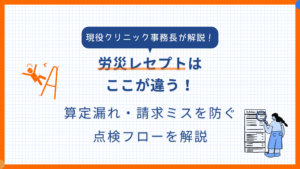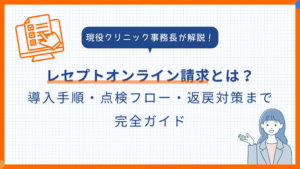レセプト月遅れとは?原因と経営リスク・解決策を徹底解説!
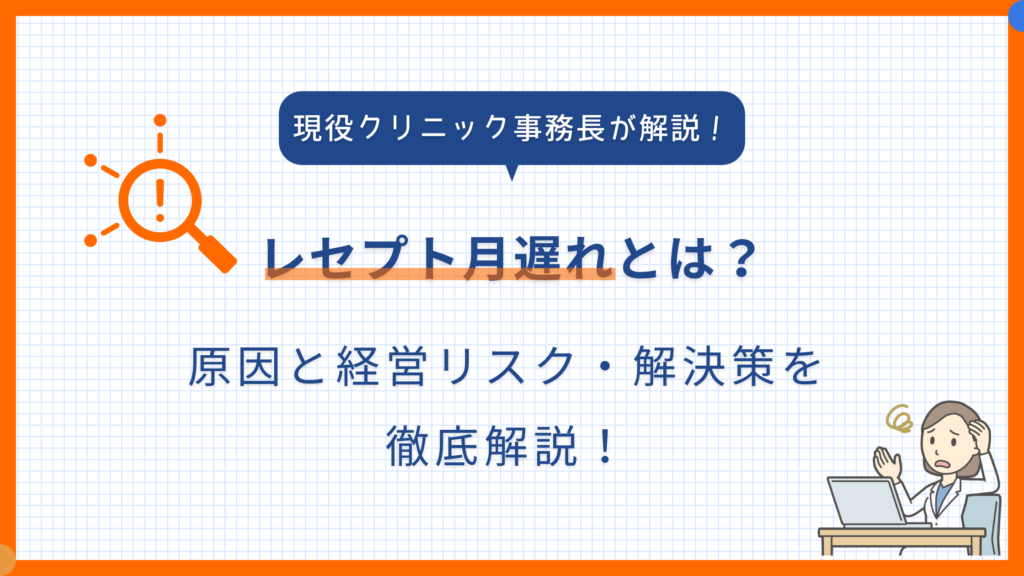
レセプト請求は、診療報酬を安定して回収するために、毎月10日までの提出期限を守ることが鉄則です。
しかし、現場では「月遅れ請求」が発生するケースが後を絶ちません。
月遅れが続くと、入金遅延によるキャッシュフロー悪化や業務負担増につながり、クリニック経営に深刻な影響を与えます。
本記事では、月遅れ請求とは何か、発生する原因、実際の事例、防止策を詳しく解説します。

株式会社パドルシップ 代表取締役
京都大学卒、京都大学大学院修了
総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。
江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。
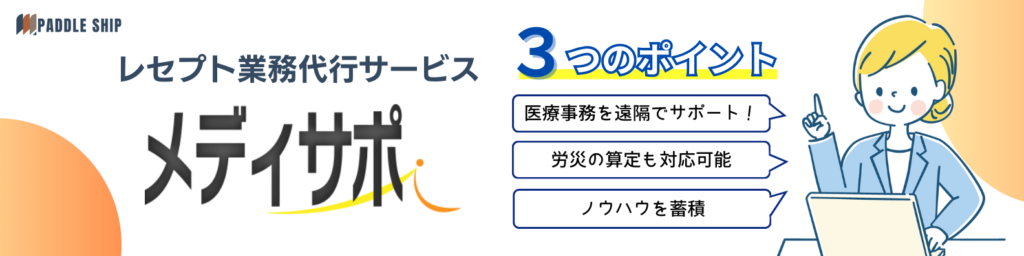
1. レセプトの月遅れ請求とは?
月遅れ請求とは、本来請求すべき月にレセプトを提出できず、翌月以降に請求することを指します。
審査支払機関(支払基金・国保連)への提出期限は、診療月の翌月10日頃が一般的です。
この期限を過ぎると「月遅れ」となり、次のようなデメリットがあります。
- 診療報酬の入金が1カ月以上遅延
- 返戻・査定対応の複雑化
- 翌月以降の業務にしわ寄せが発生
月遅れは単なる業務遅延ではなく、クリニック経営に直接影響する重大なリスクです。早期対策が重要です。
2. 月遅れが発生する原因【医療機関側・患者側】
月遅れは、医療機関側の業務体制によるものと、患者さんの事情によるものの両方で発生します。
まずは、どのような要因で月遅れが起きるのかを理解することが、改善の第一歩です。
医療機関側の原因
- カルテ入力の遅れ:医師の入力未完了、診療記録が不十分
- レセプト点検の時間不足:業務逼迫により確認作業が後手に
- 返戻対応に時間を取られる:修正対応が長引くケース
- システム障害:レセコン・電子カルテの不具合による処理遅延
- 新人教育不足:入力不備・加算漏れが多発
患者さん起因で発生する月遅れの事例
① 保険証忘れで一旦自費会計
受診時に保険証を忘れ、患者が自費で一時会計を済ませた後、翌月以降に保険証を持参し、返金・レセプト請求をやり直すケース。
対策
- 保険証確認の徹底(受付時に「当月確認済み」フラグをチェック)
- 未確認患者の管理リストを作成し、早期対応
② 生活保護の医療券が未着
生活保護の新規患者で、受診時に医療券が未発行。発行後に請求するため、翌月以降にずれ込む。
対策
- 医療券発行状況の定期確認
- 保留患者リストの進捗管理
③ 労災・自賠責書類の未提出
労災や交通事故患者が、必要な証明書類を提出しないまま治療を続けるため、請求を保留。
対策
- 初診時に書類提出期限を案内
- 提出状況の一覧管理とリマインド徹底
④ 高額療養費制度の認定証未提出
限度額適用認定証が遅れて提出され、通常請求後に再処理が必要になるケース。
対策
- 初診時の案内+SMSや電話でのリマインド
⑤ 公費(難病・小児慢性)の更新遅延
有効期限切れの受給者証が未更新のため、請求を一時保留。
対策
- 有効期限管理をシステムで実施
- 更新案内を期限1カ月前に送付
⑥ 氏名・住所変更や資格喪失
転職や住所変更により、保険資格が変更されており、確認できないケース。
対策
- オンライン資格確認システムの活用
- 月初の資格確認を徹底
3. 月遅れが経営に与える影響
月遅れは単なる請求遅延ではなく、クリニック経営の安定性や信頼性を大きく損なう要因になります。以下に、その具体的な影響を整理します。
① 診療報酬の入金サイクル遅延によるキャッシュフロー悪化
レセプトの請求は、通常、診療月の翌月10日頃までに提出し、入金はさらに1カ月後です。
しかし、月遅れが発生すると、本来翌々月に入るはずの入金が1カ月以上遅延します。
その結果、以下の問題が発生します。
- 薬剤・医療材料の仕入れ費用の支払いが圧迫される
- スタッフの給与や外注費の支払いに余裕がなくなる
- 設備投資や新規サービス導入など、経営判断が後ろ倒しになる
キャッシュフローはクリニック運営の命綱であり、遅延は経営全体のリスクを高める重大な要因です。
② 翌月以降の業務負担増加
月遅れが1件でも発生すると、その修正や請求処理を翌月に回さざるを得ません。
これにより、翌月の通常業務に加えて、前月分の処理が追加され、業務の二重負担が発生します。
さらに、複数月で月遅れが積み重なると、
- 「どの患者の請求が未処理か」把握するのに時間がかかる
- チェック漏れや再請求漏れが起こりやすくなる
- 残業や休日出勤が常態化し、スタッフの疲弊や離職リスクが増大
③ 信頼性低下とコンプライアンスリスク
月遅れが頻発すると、支払基金や国保連との関係性にも影響します。
- 提出遅延が常態化すると、審査側から「請求管理ができていない医療機関」と見なされる
- 診療報酬改定時など、請求ルールの変更に対応しきれず、査定・返戻リスクが増加
- 経営データの正確性が損なわれ、金融機関や監査対応にも支障が出る
こうした信頼性低下は、医療機関のブランドや経営の持続性にも直結します。
④ 収益機会の損失
請求の遅れや不備により、期限内に正しく請求できなかった場合、未収や算定漏れが固定化するリスクがあります。
特に、以下のケースでは致命的な損失につながります。
- 返戻や査定で再請求期限を過ぎ、報酬が回収できない
- 患者情報の更新漏れで資格喪失を見逃し、不請求になる
- 労災や自賠責など、特殊な請求で手続きが遅れ、費用請求が不可能になる
これらは、目に見えにくいが非常に大きな経営ダメージです。
4. 月遅れ防止のための実践的対策【5ステップ】
月遅れ防止には、「仕組みづくり」×「スタッフ教育」×「患者フォロー」が重要です。
医療機関側の業務起因だけでなく、患者起因の月遅れを未然に防ぐための具体策を5つにまとめます。
① カルテ入力の即日完結を徹底
医師のカルテ入力や診療内容の確定が遅れると、レセプト点検自体が始められず、結果的に月遅れの大きな要因となります。
対策ポイント
- 「診療日当日入力完了」のルール化
医師とスタッフ間で業務ルールを統一し、診療終了後の入力確認を必須化します。 - 未入力リストの毎日確認
電子カルテのレポート機能を使い、未入力件数を可視化。 - リマインド仕組みの導入
メッセージ通知や受付チェックで、入力未完了が残らないようにする。
② レセプト点検の前倒し
月末~翌月初に点検作業を集中させると、短期間で大量のレセプトを処理しなければならず、誤りや見落としが増加します。
対策ポイント
- プレ点検の導入
月末前に進捗確認を行い、入力不備・算定漏れを早期に発見。 - チェックリストでの標準化
「病名と行為の整合性」「加算条件」「資格確認」などをまとめた院内ルールを整備。 - システムのアラート設定
電子カルテやレセコンで「病名未登録」「資格不明」などを自動検知する機能を活用。
③ 患者情報の定期確認と更新管理(患者起因対策の中心)
患者起因の月遅れを防ぐには、患者との情報共有とフォローアップが重要です。
特に「保険証忘れ」「公費医療券未着」「労災・自賠責の書類遅れ」などは、事前対応でほとんど防げます。
3-1 保険証忘れへの対策
- 月初確認を徹底
月初に全患者へ「保険証確認」を実施。オンライン資格確認も積極活用。 - 再来受付での確認
電子カルテに「今月確認済」フラグをつけ、未確認者は受付で再度確認。 - 忘れた場合の即対応
自費請求時には「必ず期限(例:1週間以内)で持参」を案内し、SMSや電話でリマインド。
3-2 公費医療券・受給者証未着の対策
- 有効期限の管理表を作成
難病・小児慢性・生活保護などの有効期限を一覧化し、期限1カ月前に患者へ更新案内。 - 役所への進捗確認
医療券の発行遅延が疑われる場合は、福祉課や自治体担当へ早期確認。
3-3 労災・自賠責の書類未提出
- 初診時の案内徹底
必要書類一覧を渡し、提出期限を説明。 - リマインド対応
未提出者には診療後にSMSや電話でフォローし、提出を促す。
3-4 高額療養費・限度額認定証の未取得
- 案内とサポート
初診時に制度の説明をし、申請手順を案内。 - 未提出患者へのフォロー
認定証が届いたら必ずコピーをもらう運用を徹底。
3-5 氏名・住所・勤務先変更対応
- 受付時にヒアリング
「保険証の内容に変更はありませんか?」を必ず確認。 - マイナ保険証の活用
資格確認の精度を高め、紙の保険証トラブルを防ぐ。
④ 外部代行の活用
スタッフ不足や専門知識不足によって、請求業務や返戻対応が遅れ、月遅れにつながるケースは非常に多いです。
対策ポイント
- レセプト代行サービスの利用
外部の専門チームにレセプト点検・返戻対応を委託し、業務負担を軽減。 - ダブルチェック体制
提出前に二重・三重のチェックを行うことで、漏れを防止。 - 診療科別サポート
整形外科、内科など科目特有の返戻リスクに応じた対応が可能。
⑤ スケジュールの「見える化」
請求締切や各種確認タスクが個人任せになっていると、作業の抜け漏れや遅延が発生しやすくなります。
対策ポイント
- 請求関連カレンダーの共有
月初に「請求スケジュール」をスタッフ全員で確認。 - 重要タスクの明確化
「プレ点検日」「保険証確認日」「外部提出日」などをカレンダーに設定。 - 進捗共有ツールの活用
Googleスプレッドシートやタスク管理ツールで業務を可視化し、抜け漏れ防止。
5. 成功事例|内科クリニックで未請求を回収し経営改善
ある内科クリニックでは、医師・医療事務ともにレセプト請求に関する知識が不十分で、月遅れ対応という概念自体が理解されていませんでした。
そのため、次のような問題が発生していました。
- 保険証忘れで自費対応した患者の精算を放置
- 公費医療券未着や資格変更患者の請求が未処理
- 生活保護・労災の未請求案件が多数存在
これらは本来、期限内であれば対応可能なケースでしたが、放置されたままになっていたため、患者負担分や保険負担分が回収できず、収益に大きな影響を与えていました。
弊社の対応
弊社がレセプト代行サービスで介入し、次の施策を実施しました。
- 未請求案件のリスト化
月遅れ案件をすべて抽出し、患者負担分と保険負担分を整理。 - 優先度をつけて対応
時効リスクが高い案件から順に処理し、再請求を実施。 - 患者への案内とフォロー
未精算の患者には電話や郵送で精算案内を実施。 - 院内フローの改善提案
保険証確認・公費確認・書類回収の運用を標準化し、再発防止策を提案。
成果
- 未請求分をすべて回収(患者負担分+保険負担分)
- 約100万円以上の収益損失を防止
- 月遅れ案件の進捗管理が仕組み化され、翌月以降は月遅れ件数を改善
6. まとめ|月遅れ防止は経営安定の第一歩
レセプトの月遅れは、単なる請求遅延ではなく、経営に深刻な影響を及ぼすリスク要因です。
入金サイクルの遅延、業務負担の増大、スタッフの疲弊、さらには未収や査定による収益損失につながります。
一度発生すると翌月以降にも影響が連鎖し、取り戻すのが難しくなるため、早期の仕組み化と運用改善が不可欠です。
今回ご紹介した対策のポイントは以下のとおりです。
- 医師とスタッフでカルテ入力・請求ルールを徹底
- プレ点検を導入し、早期に不備を解消
- 保険証や公費、労災・自賠責案件の管理を仕組み化
- 外部代行を活用して業務負担とリスクを軽減
- 請求スケジュールを全員で共有し、抜け漏れゼロを実現
患者起因のトラブルやスタッフ不足など、現場の課題は一朝一夕には解消できません。
しかし、仕組みと専門的なサポートを組み合わせることで、月遅れは確実に減らせます。
当社では、レセプト請求業務の効率化と返戻率削減に強い「メディサポ」を提供しています。
「月遅れが多い」「未請求が発生している」「返戻や算定漏れも気になる」というクリニック様は、ぜひ一度ご相談ください。
未回収リスクをゼロにし、経営の安定を実現するサポートをご提案します。
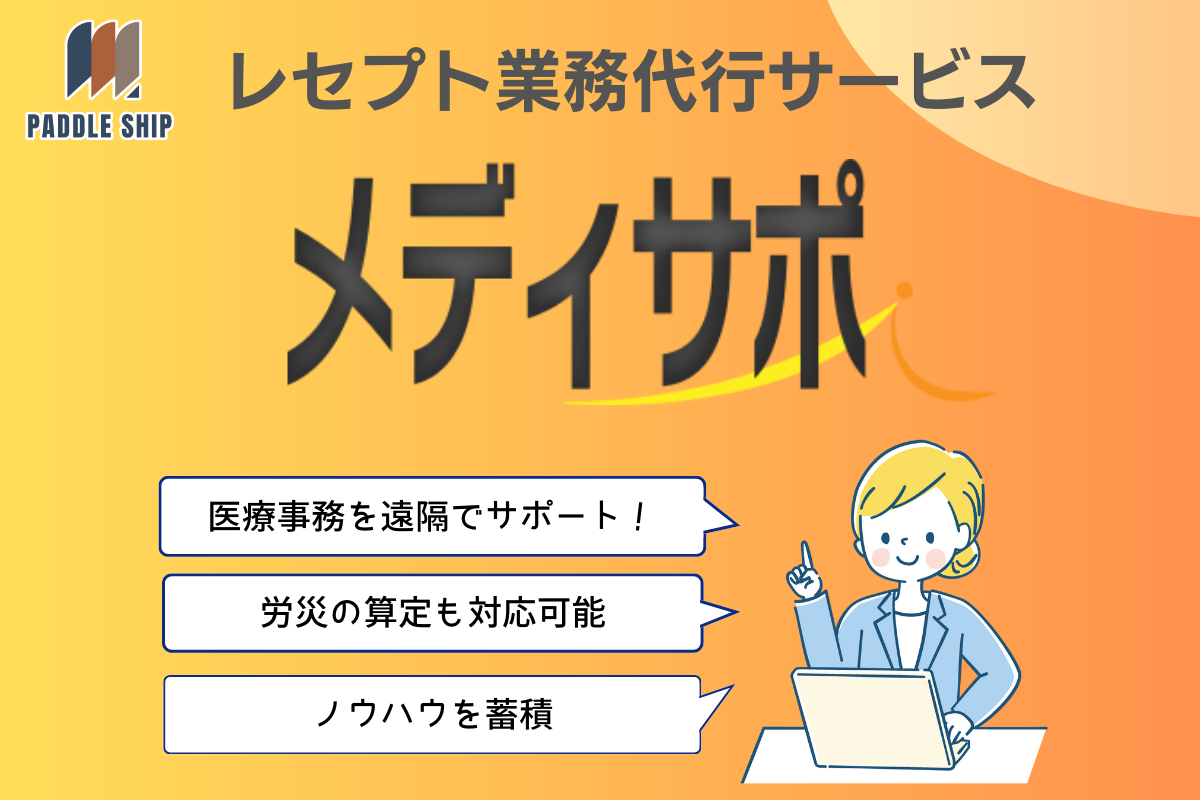
医療事務の人材採用・育成の負担を解消
「レセプト業務代行」
電子カルテデータより集患や運用の課題を抽出
クリニック事務長が作った経営分析ツール
「メディカルボード」
電子カルテデータより集患や運用の課題を抽出
- データ処理の煩雑さ/工数の増大
- 分析の切り口がわからない
現場でのこのような課題を解決するために、
電子カルテのデータを瞬時に見える化するツールを開発しました。