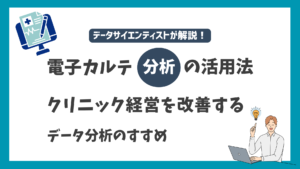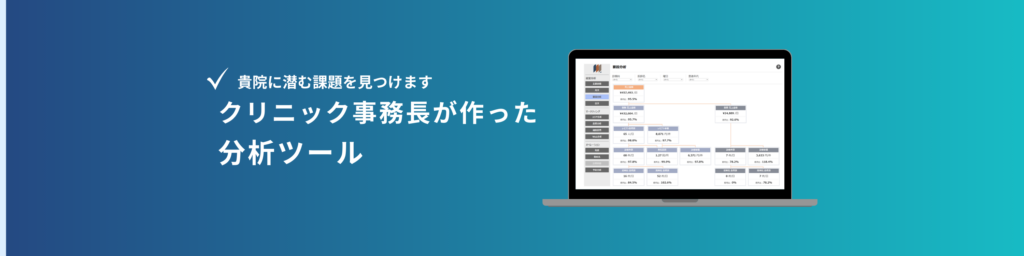【2025年対応】電子カルテ移行の完全ガイド|紙カルテからスムーズに切り替えるポイントとは?
開業医としてクリニックを運営していく立場になり、医師としてよい医療を提供することはもちろん、経営者として自院の経営をしっかり分析していくことも非常に大切です。とはいえ、経営分析の経験がなければ、どのように実施するのかわからないことも多いと思います。
そこで、クリニックの事務長を経験した筆者が、効率的に経営分析を行うためにダッシュボードと呼ばれる経営の可視化ツールを開発しました。
実際に当該クリニックにも導入したことで種々データを用いて経営改善の議論がしやすくなったことや分析するためのデータの前処理時間を削減できたことなど様々な効果が得られました。ぜひ皆様のクリニックでも活用できたらという想いで記事を書いていきます。
ご参考ください。

株式会社パドルシップ 代表取締役
京都大学卒、京都大学大学院修了
総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。
江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。
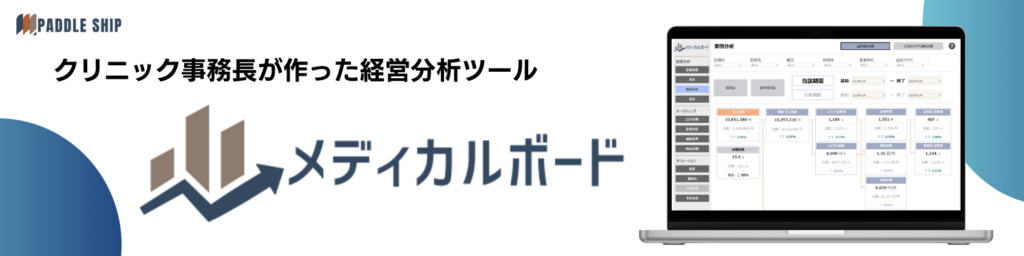
今なぜ「電子カルテ移行」が求められるのか?
医療DXの推進に伴い、2025年から段階的に「電子カルテの標準化・義務化」が進んでいます。クリニックでも例外ではなく、紙カルテや旧型電子カルテからの「移行」が現実的な課題となってきました。
「まだ紙カルテを使っている」
「昔導入した電子カルテが使いづらい」
そんな医院こそ、今が見直しと移行のチャンスです。
本記事では、電子カルテ移行を検討している開業医・事務長の方向けに、以下の内容を解説します。
- 電子カルテ移行が必要とされる背景
- 移行にあたっての手順とスケジュール
- よくあるトラブルと回避ポイント
- おすすめの補助金制度とコスト対策
- 院内スタッフへの浸透方法
電子カルテ移行の背景|医療DXと義務化の流れ
厚生労働省は「全国医療情報プラットフォーム構想」を掲げ、診療情報の共有と一元管理を進めています。この中で、電子カルテの導入と標準化が大きな柱とされており、いずれすべての医療機関において導入が求められる見込みです。
特にクリニックでは、以下のような背景から移行が加速しています。
- オンライン資格確認の義務化(2023年~)
- 医療DX推進体制整備加算の算定要件(2024年度~)
- 紙カルテによる業務負担やリスクの増加
- クラウド型電子カルテの進化と低コスト化
以下、概要をご説明します。
オンライン資格確認の義務化(2023年4月~)
2023年より、保険証の確認にマイナンバーカードを利用する「オンライン資格確認」の運用が義務化されました。
このオンライン資格確認を適切に運用するためには、電子カルテやレセプトコンピュータとの連携が不可欠です。
紙カルテのままでは、保険資格情報の取り扱いや自動連携ができないため、結果的に手作業が増え、業務効率の低下や人的ミスのリスクが高まります。
医療DX推進体制整備加算の算定要件(2024年度~)
2024年度の診療報酬改定では、新たに「医療DX推進体制整備加算」が設けられました。この加算を取得するためには、次の3つの要件を満たす必要があります。
- オンライン資格確認の導入
- マイナンバーカードによる情報取得の運用
- 電子カルテを導入していること
つまり、電子カルテを導入していないクリニックは、この加算を算定できないことになります。今後、他の加算と連動する可能性もあるため、早期の移行が重要とされています。
紙カルテによる業務負担やリスクの増加
紙カルテを使い続けることによるデメリットも年々大きくなっています。
- 保管スペースが不足する
- 過去の情報検索に時間がかかる
- 医師やスタッフ間の情報共有が困難
- 災害・火災などによる物理的な損失リスク
一方で電子カルテであれば、検索・共有・バックアップが容易になり、日々の業務効率が大きく向上します。
クラウド型電子カルテの進化と低コスト化
近年は、クラウド型の電子カルテシステムが急速に普及しており、導入ハードルも大きく下がっています。
- オンプレミス型より初期コストが低い
- 設備投資が不要(サーバーや専用機器不要)
- インターネット環境があれば院外でもアクセス可能
- セキュリティ面でも大手事業者が継続的に対応
これにより、中小規模のクリニックでも、コストを抑えながらDXに対応できるようになってきました。
電子カルテ移行の流れ|5つのステップ
① 現状分析(紙カルテ or 旧システムの課題洗い出し)
② 製品選定(クラウド or オンプレ型などの比較)
③ データ移行計画(診療データ、レセプト情報の整理)
④ テスト運用・トレーニング(スタッフ教育)
⑤ 本稼働・アフターサポートの整備
ポイントは、単なる「導入」ではなく、既存の業務に合わせた“移行設計”を丁寧に行うことです。各ステップごとにポイントを見ていきます。
ステップ①:現状分析と課題の洗い出し
まずは、自院の現在の運用状況を可視化しましょう。
- 紙カルテの使用状況(どの程度の保管があるか)
- 過去データの保管形式(紙・Excel・旧レセコンなど)
- スタッフのITリテラシーや業務フロー
- 現在の診療科・診療スタイルに合うシステム要件
この段階で「何を残し、何を捨てるか」を判断することが、移行全体の成否を分けます。
ステップ②:システム選定とベンダー比較
次に、自院に合った電子カルテの選定を行います。
- クラウド型 or オンプレ型?
→ 多くのクリニックでは、初期費用が抑えられ、外出先からもアクセス可能な「クラウド型」が主流となりつつあります。 - レセコンとの連携は?
→ 電子カルテとレセプトコンピュータ(レセコン)の一体型 or 連携型の選定も重要です。 - 美容や自由診療への対応は?
→ 自由診療の比率が高いクリニックでは、カスタマイズ性のあるカルテがおすすめです。
最低でも3社程度は比較検討し、デモを見た上でスタッフの意見も反映しましょう。
ステップ③:データ移行とバックアップの準備
もっとも慎重に進めたいステップが、既存データの移行です。
- 紙カルテのスキャン・要約データの取り込み
- 旧電子カルテやレセコンからのデータ抽出
- 患者基本情報(氏名・保険情報・来院履歴など)の整備
- 移行期間中の二重入力リスクの回避策
ベンダーと「どこまで自動移行できるか」「手入力すべき項目は何か」を明確にしておくことが大切です。
ステップ④:テスト運用とスタッフトレーニング
本格稼働の前に、「診療の流れ」を再現するテストを行います。
- 外来受付〜診察〜会計までの流れを確認
- 実際の症例を使って模擬入力・操作練習
- リーダブルなマニュアルやショートカットキー一覧を準備
- スタッフ間の質問・意見共有の場(朝礼など)を設定
受付・看護師・医師の3職種それぞれにトレーニングを実施。「わからないまま本稼働」にならない工夫が重要です。
ステップ⑤:本稼働とアフターサポート体制の整備
実際の本番稼働です。
- 初週は「予約枠を少なめに調整」しておくのが理想
- ベンダーの即時対応窓口があるか確認
- 操作で困った時の社内担当者(ITリーダー)を明確に
- 導入から1か月後に実際に操作する「現場の声」をフィードバックする場を設ける
稼働後も「運用しながら改善していく姿勢」が、電子カルテを定着させる鍵です。
電子カルテ移行のトラブルと回避策
トラブル例①:診療データの欠損
→ 導入業者に「過去カルテの移行実績」を必ず確認しましょう。データの書式や記載法が異なると、移行時にデータが欠損する可能性があります。
トラブル例②:業務効率の一時低下
→ 操作性の悪い電子カルテを導入すると、移行直後に診療効率が落ちるリスクあり。直感的に使えるインターフェースか?は要チェックです。
トラブル例③:スタッフの抵抗感
→ 導入前の「事前説明会」や「トライアル操作期間」が重要です。特に事務・看護師の声を取り入れることで、スムーズな定着が期待できます。
補助金・コスト対策も要チェック
● IT導入補助金(2025年版も継続)
- 最大450万円程度まで補助可能(対象条件あり)
- 電子カルテ本体だけでなく、周辺機器・教育費も含まれる場合あり
2025年版の詳細は公式のサイトをご確認下さい。
IT導入補助金2025 https://it-shien.smrj.go.jp/
● 医療DX推進体制整備加算
- 電子カルテにすることで診療報酬の加算対象になりえます。
- 算定額は少額でも、他の加算と連動する可能性が高く、将来的に経営へのインパクトも高まると考えられます。
● クラウド型なら月額制で初期費用を抑えられる
オンプレミス型に比べて、初期導入コストを数十分の一に抑えられるクラウド型も増えており、コスト面でのハードルは確実に下がってきています。
まとめ|電子カルテは「導入」より「移行」の質が重要
電子カルテの移行は、診療・経営・スタッフ業務に大きく関わる重要な意思決定です。
今後、義務化や情報共有インフラとの接続が進む中、単なる“置き換え”ではなく、
✅ 業務フローの最適化
✅ 経営データの可視化
✅ 医療の質の向上
といった観点をもって「移行プロジェクト」として取り組むことが求められます。
導入支援・業務改善のご相談も承っています
私たちは、クリニックに特化した電子カルテ移行支援や、データ活用支援(経営のダッシュボード化)を行っています。
「うちは紙カルテだけど大丈夫?」「レセコンと連携したい」など、
些細なことでもお気軽にご相談ください。
◆電子カルテに移行したら、データを自動で取得・可視化できるツールもある
クリニックでは、院長自身が経営・診療・マネジメントの全てを担っているケースが多く、「分析にまで手が回らない」というのが現実です。
そこで注目されているのが、電子カルテの経営可視化ツール(ダッシュボード化)です。
紙カルテでは実現できなかった経営データ可視化の自動化ツールです。
毎日(あるいは月次で)更新できるツールですので、分析を行うためのデータ収集、加工などのいわゆる前処理が必要ありません。
そのため、本来の診療に集中しながら経営改善を図ることができます。
筆者はクリニックの事務長業務を経験し、様々な経営指標を分析してきました。
データが散らばっていたり、意図したまとめ方がすぐにわからないなど様々な分析業務の非効率さを味わってきました。
そこで経営分析をしようにも、まず何からしたらいいかわからない方、データの前処理が面倒だと感じる方に対し、経営分析が簡易的にできるツールを開発しました。
今後も使い方を開発しより良いツールにバージョンアップしていく予定ですが、
少なくとも皆様の、電子カルテやレセコンのデータをエクセルにまとめたり、どのように可視化するのかを考える無駄な時間を削減したいと思い本ツールを開発しました。
是非一度使ってみてください!お問い合わせお待ち申し上げます。