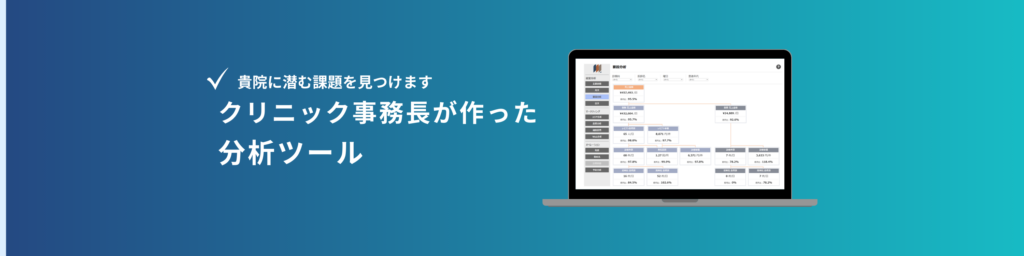【2025年版】電子カルテ義務化とは?クリニックが知っておくべき対応とポイント
開業医としてクリニックを運営していく立場になり、医師としてよい医療を提供することはもちろん、経営者として自院の経営をしっかり分析していくことも非常に大切です。とはいえ、経営分析の経験がなければ、どのように実施するのかわからないことも多いと思います。
そこで、クリニックの事務長を経験した筆者が、効率的に経営分析を行うためにダッシュボードと呼ばれる経営の可視化ツールを開発しました。
実際に当該クリニックにも導入したことで種々データを用いて経営改善の議論がしやすくなったことや分析するためのデータの前処理時間を削減できたことなど様々な効果が得られました。ぜひ皆様のクリニックでも活用できたらという想いで記事を書いていきます。
ご参考ください。

株式会社パドルシップ 代表取締役
京都大学卒、京都大学大学院修了
総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。
江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。
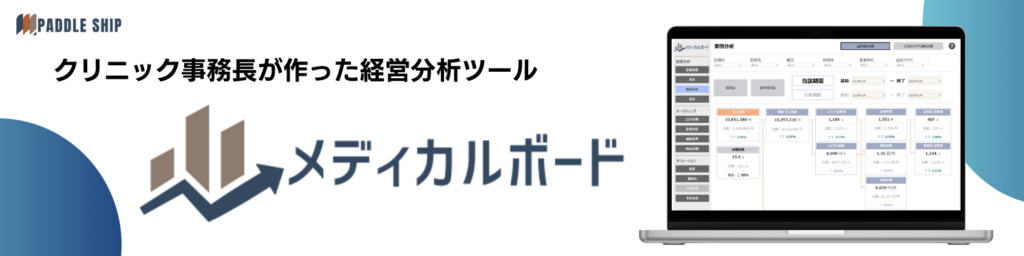
はじめに:電子カルテは「義務化の時代」へ
現在、政府は医療DX(デジタルトランスフォーメーション)を本格的に推進しており、その中心にあるのが「電子カルテの標準化と義務化」です。特に2025年以降、段階的に義務化の動きが強まり、無床診療所でも例外ではありません。
本記事では、無床クリニックの開業医・事務長の方に向けて、
- 電子カルテ義務化の背景と概要
- 対象となる施設とスケジュール
- 導入に向けた実務的な対応
- 義務化によるメリットと注意点
- スムーズに対応するためのアドバイス
を、クリニックの現役事務長がわかりやすく解説します。
電子カルテ義務化とは?医療DXの中核政策
背景にあるのは「全国医療情報プラットフォーム構想」
厚生労働省は、2025年度を目途に「全国医療情報プラットフォーム」を構築し、電子カルテ情報を医療機関間で安全かつ効率的に共有できるようにする方針です。この実現に向けて、電子カルテの導入と「標準化」が強く求められています。
義務化のスケジュール(※2024年現在の発表を元に記載)
| 年度 | 主な動き |
|---|---|
| 2023年度 | 標準仕様策定(電子カルテ情報の交換様式) |
| 2024年度 | 大病院・一部の医療機関で標準仕様に基づく導入がスタート |
| 2025年度以降 | 医療機関の規模に応じて段階的に導入が義務化へ |
無床診療所は義務化の対象になるのか?
現時点で「○年までに導入義務」と明記されているのは大規模病院が中心ですが、最終的にはすべての医療機関が電子カルテ導入を求められる方向です。つまり、クリニックも対象となることはほぼ確実といえます。
さらに、
- 地域連携(診療情報提供書など)
- オンライン資格確認の義務化(2023年4月〜)
- 医療DX推進体制整備加算の取得要件
などが進む中で、「紙カルテで対応できない場面」が今後ますます増えていきます。
電子カルテ義務化がもたらすメリット
- 医療の質向上
患者さんの情報を素早く参照・共有できるため、医療の安全性が高められます。また、紹介状や検査結果なども一元管理できるため、診察がしやすく、効率が高まると考えられます。 - 事務作業の効率化
診療記録・レセプト業務がデジタル化されることで、事務スタッフの作業量削減・ミス防止につながります。 - 経営分析への活用
蓄積された診療データをもとに、患者数・診療単価・傷病・処置別の傾向分析が可能になります。したがって、経営判断の「見える化」が容易になります。 - 医療DX加算の算定
「医療DX推進体制整備加算」(2024年診療報酬改定)では、電子カルテ導入とオンライン資格確認システムの活用が前提条件になりました。算定額は少額でも、他の加算と連動する可能性が高く、将来的に経営へのインパクトも高まると考えられます。
導入・移行の際に注意すべきポイント
導入時のコストと補助金の活用
電子カルテは本体費用+初期設定費用+月額使用料がかかります。ただし、IT導入補助金等の補助金を活用できるケースもあるため、補助金を確認しておくのが良いでしょう。
中小規模のクリニックでは、いわゆる大病院で使われているようなオンプレミス型(院内設置型)に必ずしもする必要はなく、昨今ではWebを介して利用するクラウド型のシェアが伸びてきています。初期費用は各段にオンプレミス型と比較して安く、往診など院外にいるときでも閲覧できるように設定できることから、クラウド型に移行する流れができてきていると思います。
スタッフ教育と業務フローの再構築
導入初期はこれまでに慣れた業務フローを変更することになりますので、診療効率が一時的に落ちることもあります。またPCの操作に慣れない現場スタッフのリテラシー問題やマニュアルの整備が肝ではないでしょうか。
自院の業務に合ったカルテ選び
たとえば、保険医療主体か、美容などの自由診療主体か、レセコン一体型か、クラウド型かオンプレ型かなど、クリニックの規模や運用に合った製品選定が必要です。こちらについてはまた別の機会にご紹介したいと思います。
まとめ:今こそ「紙カルテ卒業」の準備を
電子カルテの義務化は、もはや先延ばしできない課題です。特にクリニックでは、「診療・経営・事務の効率化」を同時に実現できる大きなチャンスとも言えます。
今後は、単に導入するだけでなく、「どう経営に活かすか」「データをどう活用するか」が重要になってきます。電子カルテを「記録の道具」から「経営のパートナー」へ、といった意識改革が重要だと考えています。本格的な義務化を前に、今から情報収集と準備を進めておきましょう。
弊社では、クリニック現場での電子カルテ導入・データ活用支援を行っており、実務に即したサポートをご提供可能です。「うちの規模でも義務化対象になる?」「どんな製品が向いている?」などのご相談も可能ですので、お気軽にご連絡ください。
◆電子カルテに移行したら、データを自動で取得・可視化できるツールもある
クリニックでは、院長自身が経営・診療・マネジメントの全てを担っているケースが多く、「分析にまで手が回らない」というのが現実です。そこで注目されているのが、電子カルテの経営可視化ツール(ダッシュボード化)です。
紙カルテでは実現できなかった経営データ可視化の自動化ツールです。毎日(あるいは月次で)更新できるツールですので、分析を行うためのデータ収集、加工などのいわゆる前処理が必要ありません。そのため、本来の診療に集中しながら経営改善を図ることができます。
筆者はクリニックの事務長業務を経験し、様々な経営指標を分析してきました。データが散らばっていたり、意図したまとめ方がすぐにわからないなど様々な分析業務の非効率さを味わってきました。
そこで経営分析をしようにも、まず何からしたらいいかわからない方、データの前処理が面倒だと感じる方に対し、経営分析が簡易的にできるツールを開発しました。
今後も使い方を開発しより良いツールにバージョンアップしていく予定ですが、少なくとも皆様の、電子カルテやレセコンのデータをエクセルにまとめたり、どのように可視化するのかを考える無駄な時間を削減したいと思い本ツールを開発しました。
是非一度使ってみてください!お問い合わせお待ち申し上げます。