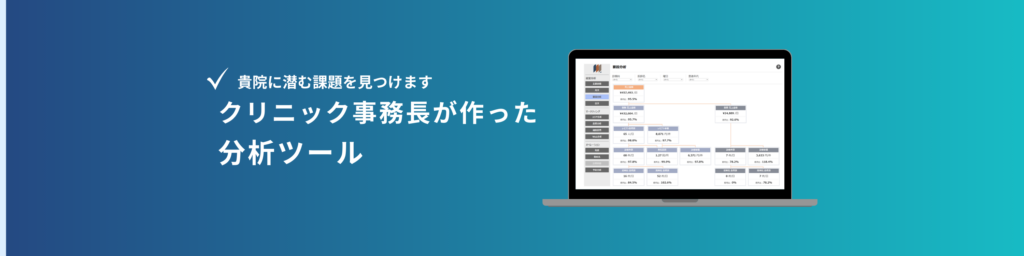デジカルのデータを活かす!分析が自動で行えるツールとは?
クリニックを運営していく立場で、
特にエムスリーデジカル(M3 DigiKar、以下デジカル)を利用されている先生の中には、
- 日々の診療で手一杯で、自院の経営を分析するところまで手が回っていない・・・
- デジカルから出力できるデータを、もっと効率よく分析できないか・・・
などと感じられたことはないでしょうか。
分析のためには、デジカルからCSVを出力し、Excelで手作業の集計をして、結果を見ながら集計をやり直して・・・
そんな負担を減らしながら、必要な数値を“見える形”で把握できる仕組みがあれば、
経営判断もスタッフとの共有も、もっとスムーズになるかもしれません。
本記事では、
デジカルから取得できるデータを手間なく活かす方法として、
現場で実際に使われている「経営分析ツール」の事例をご紹介いたします。

株式会社パドルシップ 代表取締役
京都大学卒、京都大学大学院修了
総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。
江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。
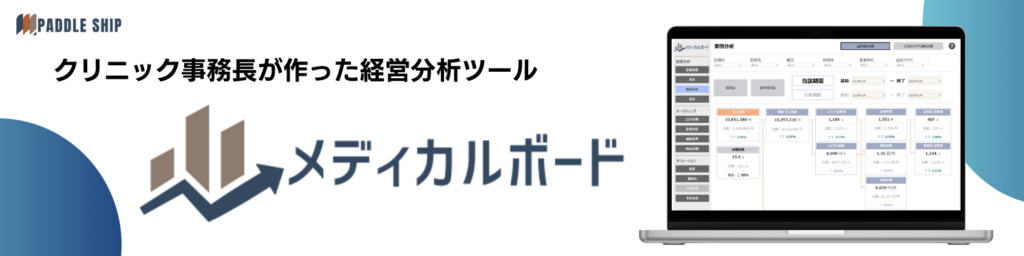
デジカルのデータ、「もっと使えたら」と感じたことはありませんか?
M3デジカル社の電子カルテ「デジカル」は、導入のしやすさやコストパフォーマンスの高さから、多くのクリニックで採用されています。
一方で、日々の診療に追われる中、「出力できるデータはあるものの、うまく活用できていない」と感じたことがある先生も少なくないのではないでしょうか。
CSV出力はできても、日常業務で使いこなすにはひと手間かかる
デジカルでは、診療実績や処置件数、請求情報などの各種データをCSV形式で出力できます。
しかし出力後はExcelで手作業の整形・集計が必要だったりと、“活用しきれていない”感覚を持たれる先生も多いようです。
また、月次レポートなどをつくろうと思っても、属人的な管理になって再現性に欠けるという声もよく聞かれます。
「診療単価が下がっている…でも原因が見えない」
実際にExcelで手間をかけて集計をしたとしても、「この変化は誰によるものか?」「曜日や時間帯の傾向は?」といった、結果を見た際に湧いてくる疑問も色々とあります。
一方、これらに答える結果を出すためには、さらに細かい分析が必要となり、そこで分析をギブアップしてしまうこともよくあります。
このように、原因を突き止める機能の不足が課題になる場面もあるのではないでしょうか。
月次集計や報告書作成が「時間がかかる仕事」になってしまう
CSVデータの抽出から月次集計、報告書作成までを手作業でこなすと、1回の業務に数時間以上かかることもあります。事務スタッフへの負担が大きく、院長ご自身が直接手を動かしているケースも少なくありません。分析や改善に向けた時間が確保できず、「とりあえず現状維持」が続いてしまう原因にもなります。
こうした課題は、電子カルテが悪いという話ではなく、「データをどう使うか」という運用側の課題とも言えるでしょう。
私自身もこのような悩みをきっかけに、別のアプローチを模索し始めました。
デジカルではここまで見える!出力できるデータとその可能性
デジカルは、さまざまな診療データを出力できる機能を備えています。ここでは、日々の診療や経営判断に活用しうる「出力できるデータ」と、そこから得られる可能性について整理してみましょう。
出力可能なデータは?|診療実績・請求・処置など多岐にわたる
デジカルでは、患者基本情報、カルテ集計、診療処置行為(薬剤含む)、傷病名一覧、レセプト関連などの各種データをCSV形式で出力することが可能です。これにより、診療件数の推移や患者数、処置件数、診療単価など、基本的な経営指標を集計することができます。
使い方次第で“経営指標”が見えてくる
これらのデータを使えば、たとえば以下のような情報が得られます:
- 曜日別の来院件数
- 医師別の診療単価や診療回数
- 患者年代別・傷病名別の傾向
上記は一見「事務的なデータ」ですが、これらデータでも工夫次第で現場や経営に役立つ“意味ある指標”として活用できます。「なんとなく忙しい」「なんとなく売上が下がっている」といった感覚に、数字という根拠を与えることができます。
ただし、そのままでは“わかりにくい”ことも多い
CSVで出力されたデータは、あくまで生データです。例えば、医師ごとの診療単価や時間帯別の傾向などを分析するには、ピボットや関数を使った加工が必要になります。こうした処理にはExcelスキルが求められ、またデータ加工にも一定の時間がかかるため、実際には活用しきれないまま終わってしまうことも少なくありません。
次章では、こうしたデータを毎月の分析に活かすために、手作業を減らし、効率的に“見える化”していく方法として、「自動化」の考え方についてご紹介します。
Excelでの集計はもう限界?分析の手間を減らす“自動化”という選択肢
デジカルから出力できるCSVデータを活用するには手作業での整形・加工が前提となることが多く、「忙しい中そこまで手が回らない」と感じている先生も多いのではないでしょうか。
「データはあるけど分析できない」その理由は“時間”と“スキル”
厚生労働省によると、医療機関の管理業務・事務業務にかかる時間は年々増加傾向にあり、医師の働き方改革においても大きな課題となっています。
▶ 厚労省:医師の働き方改革に関する資料
診療記録を見ながらデータを整理し、関数やグラフで集計結果を整える作業は、想像以上に時間を要します。特に、曜日別・医師別といった視点での分析は、Excelに慣れていないとハードルが高く、現場では後回しになりがちです。
Excel依存が招く属人化と再現性の欠如
こうした分析業務がもしできるスタッフがいた場合でも、「この分析は○○さんしかできない」といった属人化が発生しやすく、異動や退職によって業務の引き継ぎが困難になるリスクもあります。 また、月次で行う分析に時間がかかるため、タイムリーな経営判断ができないという問題にもつながりやすいのが現実です。
実際、総務省の業務自動化に関する調査でも、「属人的な情報処理がボトルネックとなっている」という指摘が多くなされています。
“集計済みデータを見るだけ”の状態に近づけるには?
こうした課題の解決には、出力されたデータを自動で加工・集計し、可視化された状態で確認できる仕組みが有効です。 いわゆる「ダッシュボード」型の分析支援ツールを活用すれば、煩雑なExcel作業を省略し、数クリックで現状を把握できる環境を整えることができます。
たとえば、曜日別の患者数や医師別の診療単価なども、自動的にグラフ化された形で確認できれば、「改善が必要なポイント」が一目でわかるようになります。
次章では、こうした“自動で見える化されたデータ”を、実際にどのように活用できるのかを具体的にご紹介します。
メディカルボードで実現する“見える化”|デジカルのデータを経営に活かす方法
ここでは、私たちが実際に開発し、現場で使用している経営分析ツール「メディカルボード」を例に、どのようにデータを可視化し、どのような経営判断に役立てているかをご紹介します。
メディカルボードとは?
メディカルボードは、電子カルテのデータをもとに、クリニックに必要な経営情報を自動的に可視化するダッシュボードツールです。具体的には、「デジカル」から取得できるデータを自動で取得し、データ分析・可視化までも一気通貫で行います。
これにより、手作業でのExcel集計を必要とせず、毎月自動で更新された可視化結果を確認することが可能です。
可視化できる具体データと分析事例
- 曜日別・時間帯別の来院数グラフ:患者数の少ない曜日・時間帯を把握し、シフト最適化に活用
- 医師別の診療単価:非常勤医師の評価やインセンティブ設計に活用
- エリア分析:来院率が高い/低いエリアを把握し、チラシ配布先やWeb広告の配信エリアの選定に活用
- 離脱患者リスト:慢性疾患患者の通院中断を把握し、フォローアップ対象を抽出
これらの分析により、「なんとなくの感覚」で決めていた人員配置や集患施策に対して、データに基づいた説明と判断が可能になりました。
スタッフ間の共有・納得を生む“経営ツール”としての活用
このように可視化された情報は、院長だけでなく、事務長、看護師、受付スタッフなどにも共有可能です。「曜日別に忙しさが違う」「広告の反応率が下がっている」など、スタッフの肌感覚を裏付けるデータがあることで、対策案への納得度や協力体制も高まります。
実際の利用例としては、以下のようなケースがあります。
<Before>
新規に分院を作ったため、事務長がその分院のチラシ配布エリアを検討していた。
・自転車圏内は、来院可能性があるため配布をする
・競合クリニックが多いエリアは、配布をしない
という方針を考えたため、理事長に伝えたところ、「こんなに来る?」「根拠は?」と言われてしまった。<After>
・チラシの反応率をエリア分析にて把握、またクリニックからの距離ごとの来院率を把握
・来院率が悪いエリアを分析し、その原因を「競合がいる」「幹線道路を挟む」と推定
・投資効果が上回るエリアを推定し、そのエリアに配布する
という方針を伝え、対策案がジャストアイデアにならず、ロジカルさが伝わることで、院長の納得感・安心感を得られた。
また、事務長の作業工数削減や心理的負担軽減にも寄与できた
また、定例のミーティングでもこのダッシュボードを使って情報共有を行うようにしたところ、スタッフからの改善提案も増えたという実感があります。数字を「経営層だけのもの」にしないことで、現場全体の一体感やコスト意識も高まってきました。
こんな場面で活用されています|メディカルボードの具体事例
メディカルボードは、単にデータを“見える化”するだけでなく、院内業務や経営判断の場面で実際に活用されています。 ここでは、クリニック経営の現場でどのような意思決定に役立っているのか、具体的なユースケースをご紹介します。
【分析視点の強化】感覚ではなく、データで判断できるようになる
たとえば、「最近、初診の患者さんが減っている気がする」「バイト医師のパフォーマンスにムラがあるかもしれない」など、日々の診療で感じる“なんとなくの違和感”。 こうした直感を裏付けるデータがあることで、必要な打ち手を冷静に検討することができます。
“可視化された指標”が、直感に頼る運営からの脱却に役立つという声も少なくありません。
【業務改善】混雑や業務負担の偏りに対し、現場と共に改善できる
曜日・時間帯別の患者数や、予約キャンセルの集中状況が可視化されることで、受付や看護師のシフト配分も見直しやすくなります。 「この時間帯は受付スタッフ2名体制が適切」「この曜日は電話が集中する」といった改善提案が、現場スタッフから自然に上がってくるようになったという例もあります。
スタッフの心理的負担を軽減しながら、サービスの質を落とさない運営が求められる中で、こうした活用は今後ますます重要になるでしょう。
【経営判断】チラシ・広告・人材コストの見直しにも貢献
「どのエリアに広告を出すか」「新しい機器のリースは費用対効果が合うか」「バイト医師のインセンティブ設計をどうするか」など、経営的な判断が必要な場面でも、メディカルボードの分析は大いに役立ちます。
「データがあるから納得できる」「数字で説明できるから院内の合意形成がスムーズ」など、日々の小さな意思決定が積み重なる医療経営の現場において、データ活用は非常に大きな意味を持つと実感しています。
実際にメディカルボードの仕様や画面を確認するためには
これまでご紹介してきた内容は、すべて実際に運用されているダッシュボードツール「メディカルボード」に基づくものです。 本ツールでは、電子カルテの出力データをもとに、経営指標や患者動向を可視化・分析することができます。
メディカルボードをお勧めするクリニック
- デジカルのデータを出力しているが、活用しきれていない
- 毎月の集計や報告に時間がかかっている
- 数字で見せたいが、どこから手をつけていいかわからない
メディカルボードの主な特長
- 電子カルテ(デジカルなど)から出力したデータをもとに可視化
- 曜日別・医師別・診療単価・離脱患者など、院内運営に関する多角的な指標を表示
- 月次更新も自動で反映
無料デモで「実際の使い方」をご確認いただけます
メディカルボードでは、無料デモをご提供しています。実際のダッシュボード画面をご覧いただきながら、
- どんなデータが見えるのか
- 自院の経営にどう活かせるか
を、貴院の状況をお伺いしながらご説明いたします。
▼ 詳細・お申し込みはこちら
https://paddle-ship.jp/medicalboard/
導入をご検討中の方は、まずは一度、ツールの仕様や表示内容をご確認いただければと思います。
また、弊社ではメディカルボード®に加えて、貴院に合わせた自動化ツールの開発(RPA開発など)も行っています。ぜひお問い合わせください。