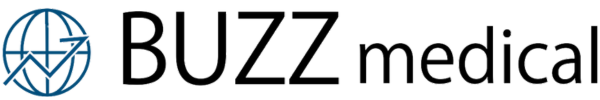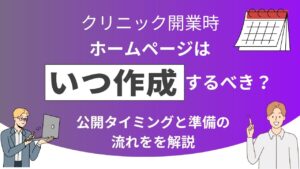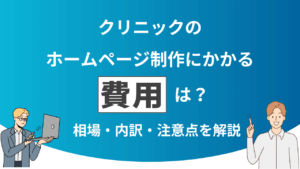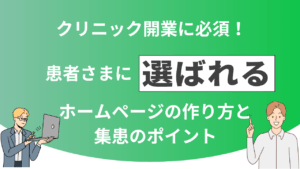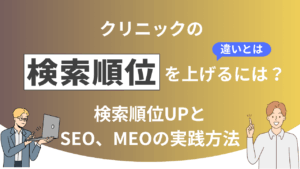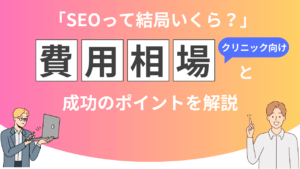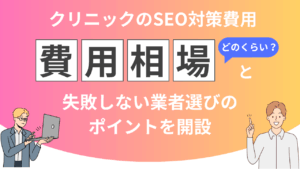開業医としてクリニックを運営していく立場になり、医師としてよい医療を提供することはもちろん重要ですが、経営者として自院の経営を見ることも非常に大切です。
特に開業前から開業初期にかけては、地域に自院を認知してもらい、患者さんに来てもらう人数を増やしていくこと(集患)が最重要課題だと思います。
集患に限らず、開業医の先生は、診療以外に労務や人事、経理、広告など業務の範囲が非常に多岐にわたります。
とりわけ昨今はWeb上にHP(ホームページ)を制作しクリニックを紹介しながら患者さんの認知獲得が求められます。ただ、Webの集患は専門性も高く、自身で進める先生は少ないのではないでしょうか。
そこで弊社では、診療と経営を両立させるため、また先生の想いを発信できるようにすることを目的としたクリニック専門のWebマーケティングサービス(BUZZ Medical)を立ち上げました。
多くの先生はWeb集患は専門業者に丸投げだと思いますし、先生自身がWeb集患の専門性を高める必要はないと思いますが、その枠組みを少しでも理解しながら業者に依頼した方がより高い効果が得られると考えています。
また昨今、美容等の自由診療の領域はもちろん、保険診療においても都市部のクリニックを中心に、web集患は基本施策に位置付けられています。
ホームページをつくることは新規開業クリニックではほぼ行われていますが、web集患の対策までは必ずしも必須ではないという位置付けで、まだ実施していないクリニックもあると思います。地域の競合クリニックが行なっている場合、ただホームページを作るだけでは立ち行かなくなる時代が来る可能性が保険診療の領域でも起こりえます。
過度に対策する必要はありませんが基本的な考え方を理解し、地域の方々への認知をwebという手段で広げていくことは必須だと筆者は考えています。
その基本的な考え方を理解する意味でも、この”お役立ち情報”では専門用語の解説やWeb専門業者が何のために何を行っているのかをわかりやすくご説明したいと思っています。
本記事では、SEOと呼ばれるWebでキーワードを検索した際に表示される順位について、その対策の考え方、進め方について解説したいと思います。

株式会社パドルシップ 代表取締役
京都大学卒、京都大学大学院修了
総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。
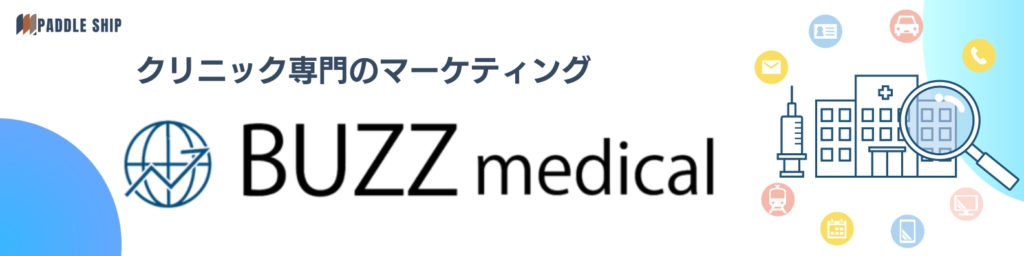
検索順位とは
まず、検索順位やSEOという考え方について簡単にご説明します。
検索順位とは、インターネット上で検索する際、特定のキーワードの検索結果において各Webサイトが表示される並び順のことです。GoogleやYahoo等の検索エンジンが各キーワードに対し、最も適切な答えが記載されたWebページだと判断した順に並びます。
一般的に、上位に表示されるほど多くの人の目に留まります。また、検索する人の使用するデバイス、年齢層等のユーザーデータ、検索の日付など、多岐にわたる要素を総合して順位が決定されています。
ちなみに、検索順位とクリック率(=「ユーザーがクリックした回数」÷「検索した際に表示された回数」)の関係は、2024年のデータ※では、1位:39.8%、2位:18.7%、3位:10.2%、4位:7.2%、5位:5.1%、6位:4.4%、7位:3.0%、8位:2.1%、9位:1.9%、10位:1.6%となっています。
検索画面の1ページあたり10位まで表示され、5位以下だと5%を切る、つまり100人検索して5人しか自身のWebサイトに訪れないということです。
この順位が各検索キーワードごとに決まっており、各Webサイトは自身のWebサイトに訪れるようにするために、狙いたいキーワードごとに人の目に留まるよう、この検索順位を競っているということです。
※引用元:Firstpagesage
https://firstpagesage.com/reports/google-click-through-rates-ctrs-by-ranking-position/
SEOとは
次にSEOという言葉があります。SEOとはSearch Engine Optimizationの頭文字ですが、日本語にすると検索エンジン最適化ということです。簡単に言い換えると、Gooogle等の検索エンジンにおいて自身のサイトの検索順位を上位に表示させるように対策することをSEO、あるいはSEO対策と言います。
上記でご説明したように、各Webサイトは各キーワードごとに自身のWebサイトが上位に表示されるように競っています。特に都市部のクリニックや美容等の自由診療の領域では、このSEO対策を行っているところが多数あり、集患対策の基本となっています。
自身のクリニックのHP(ホームページ)を作っただけでは、検索順位が他院の方が上位に表示され、せっかく良いHPを作っても訪れる患者さんは少数になってしまいます。
適切にSEO対策を実行し、少なくとも自分のクリニックの特徴を示すキーワードは上位が取れるようにしておくことは特に開業初期の段階では最重要だと筆者は考えています。
SEO対策の具体的な方法
ここまでが用語の説明ですが、具体的に”SEO対策をする”とはどういうことかをご説明します。
Googleなどの検索エンジンはロボットが毎日すべてのWebサイトを見に来ています。その一つの目的は、先述の通り検索したユーザーに対して適切な答えが記載されたページを上位に表示させるためにすべてのページで答えがどのように書かれているかを見ることです。
検索上位に表示するためのロジックは様々な要素が絡むため一義的に決まるものではありませんが、少なくともテキストデータを見に来ています。
つまり、自身のWebサイトに記事を入稿する(テキストデータをインプットする)ことが重要ということです。その記事には、あるキーワードで検索したユーザーに対して、答えを書くことが求められているため、理想的には自身の狙いたいキーワードごとに1つ記事を書くということをやっていきます。これが基本的なSEO対策になります。
検索順位を決めるロジックではないと言われていますが、Googleがサイトの品質を評価する基準は公表されていますので、詳細を確認されたい方はこちらをご確認ください。
※参考 General Guidelines(Google検索品質評価ガイドライン)https://static.googleusercontent.com/media/guidelines.raterhub.com/ja//searchqualityevaluatorguidelines.pdf
E-E-A-T
E:Experience 【経験】 例:治療実績や、先生の経験談やノウハウの共有
E:Expertise 【専門性】例:疾患、傷病に関しての詳細説明
A:Authoritativeness 【権威性】例:論文の引用や病院、公的機関からの紹介(被リンク)
T:Trust 【信頼性】例:先生の経歴紹介、口コミ
SEO対策の基本となるキーワード戦略のポイント
ここまでのご説明の通り、SEO対策では、どのキーワードで上位を目指すかという、いわゆるキーワード戦略が肝になります。ここではそのポイントについてご説明します。
キーワード戦略の前提
まず、大前提として、クリニックのSEO対策では、通常、店舗型のビジネス形態になりますので、基本的には特定キーワード(症状、病名、診療科など)×地域名でSEO対策を考えます。
「発熱 江戸川区」、「内科 二子玉川」、「睡眠時無呼吸症候群 渋谷」などです。
ここでもう一つ前提をご紹介します。一般的に、言葉には意味の包含関係があります。
内科や循環器内科などの意味の幅が広いキーワード(Bigワード)は一般的にユーザーが検索する数も多く、対策する競合も多くなり、SEO対策の難易度としては高くなる傾向があります。
難易度の高いキーワードを対策する場合、その言葉を構成する細かいキーワード(smallワード)を対策していくと、Bigワードの検索順位も相関して上位に上がります。
地域名で考えるとわかりやすいです。二子玉川 < 世田谷区 < 東京都など、地域名にも包含関係があります。包含関係の大きい方が、検索ユーザー数や競合数が多くなるイメージがつきやすいと思いますが、二子玉川にある内科のクリニックがいきなり「東京都」の対策をするのは難易度が高いということです。
この場合、「内科 二子玉川」を対策し、次に「内科 世田谷区」、そして「内科 東京」を対策(そこまで対策する必要があるかは別議論)していきます。
一方、症状、病名、診療科などの特定キーワードは、言葉の認知度によって必ずしも包含関係では説明がつかない場合もありますが、考え方としては同様です。
”症状”でいうと、内科>循環器内科>胸痛、動悸、息切れ、むくみ、不整脈などの関係があると考えられますので、「胸が痛い 二子玉川」「動悸 二子玉川」を対策していくと、「循環器内科 二子玉川」が対策されるということです。
最初は飛び石で考える
では、特定キーワードをどのように決めるかですが、まずは内科、整形外科、循環器内科など、地域における診療科の検索順位を上げることを考えます。
診療科名そのものは、クリニックのHPには必ずと言って良いほど診療科の説明文がありますし、検索するユーザーの数も多いためBigワードという枠組みに入ると考えられます。
つまり、先述の通り、診療科名、例えば”内科”を対策するためには、”内科”を構成するSmallワードを対策していくことになります。具体的には、内科系の「症状」、内科系の「疾患名」を対策します。
ここでポイントになるのが、対策するキーワードの優先順位です。対策するには基本的にはそのキーワードに対して1本記事を書くことになりますので、現実的にすべてのキ―ワードを対策することはリソースの関係上、難しいです。
また、1つのKWに対して記事を入稿し検索順位が上がってくるのが、1~3ヶ月程度かかるため、どうしても優先順位を設定する必要があります。
では、優先順位の考え方ですが、筆者は飛び石的に記事を入稿することが良いと考えております。
「飛び石的に」とは、「キーワードの意味合いや検索する患者さん層が被らないようなキーワードを設定すること」と筆者は考えており、記事を入稿し始めのHPでは、このように順番を設定するのが最も効果的だと考えています。
内科系の記事を入稿するならば、「動悸」⇒「胸痛」⇒「息切れ」⇒・・・と対策するよりも、「動悸」⇒「糖尿病」⇒「喘息」⇒・・・と対策した方が、早く色んな患者さんに自分のHPを見てもらう確率が上がるということです。
要するに、以下に気を付けながら、最初は患者さん層が被らないように意識することで、優先順位をつけるようにしましょう。
①多くの患者さんが検索するキーワードを選ぶこと = 検索ボリューム
②先生が書きやすいキーワードであること = 専門性、権威性
③クリニックとして集めたい患者さん層であること = 開業の想い、収益性
最初はこの考え方で優先順位をつけ、対策をしていきますが、記事がある程度蓄積した際の考え方については、別の記事でご紹介したいと思います。
まとめ
本記事では、検索順位、SEOなど基本的な用語の解説や、SEO対策の肝となるキーワード戦略の考え方についてご紹介しました。
ご自身でもWeb検索を日々行っていることだと思いますが、自身のHPを持ち、多くの人にHPを訪れてもらいたい場合、検索される順位を競わなければなりません。
検索順位を上げるためには、検索されるキーワードに対して自身のHPが答えとなる必要があり、答えとなっていれば検索順位が上がるというロジックをGoogle等の検索エンジンは構築しています。具体的に対策する手段としてはHPにテキスト情報をインプットする、つまり記事を執筆し入稿することが求められます。
ですので、患者さんが検索するキーワードのどれに着目し対策すべきかを検討し、対策の優先順位を決めていくことがキーワード戦略と言えるのではないでしょうか。
そのキーワード戦略の考え方は、最初はキーワードを飛び石で選ぶことをおすすめします。
検索するユーザー数(=検索ボリューム)が比較的多いキーワードを選び、患者さん層があまり被らないようにすることで、様々な方のクリニックの認知度を効率的に高める方法として良いと考えています。業者とやり取りする際に、ぜひ参考にされてはいかがでしょうか。
昨今、美容等の自由診療の領域はもちろん、保険診療においても都市部のクリニックを中心に、web集患は基本施策に位置付けられています。
ホームページをつくることは新規開業クリニックではほぼ行われていますが、web集患の対策までは必ずしも必須ではないという位置付けで、まだ実施していないクリニックもあると思います。地域の競合クリニックが行なっている場合、ただホームページを作るだけでは立ち行かなくなる時代が来る可能性が保険診療の領域でも起こりえます。
過度に対策する必要はありませんが基本的な考え方を理解し、地域の方々への認知をwebという手段で広げていくことは必須だと筆者は考えています。
弊社では、先生方のクリニックのWebにおける集患を支援するBuzz Medicalというサービスを立ち上げました。
HP制作やリニューアル、SEO対策、MEO対策、Google広告代行など、様々なWeb集患のお手伝いをしております。ぜひ一度、お問い合わせください!