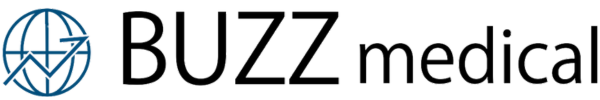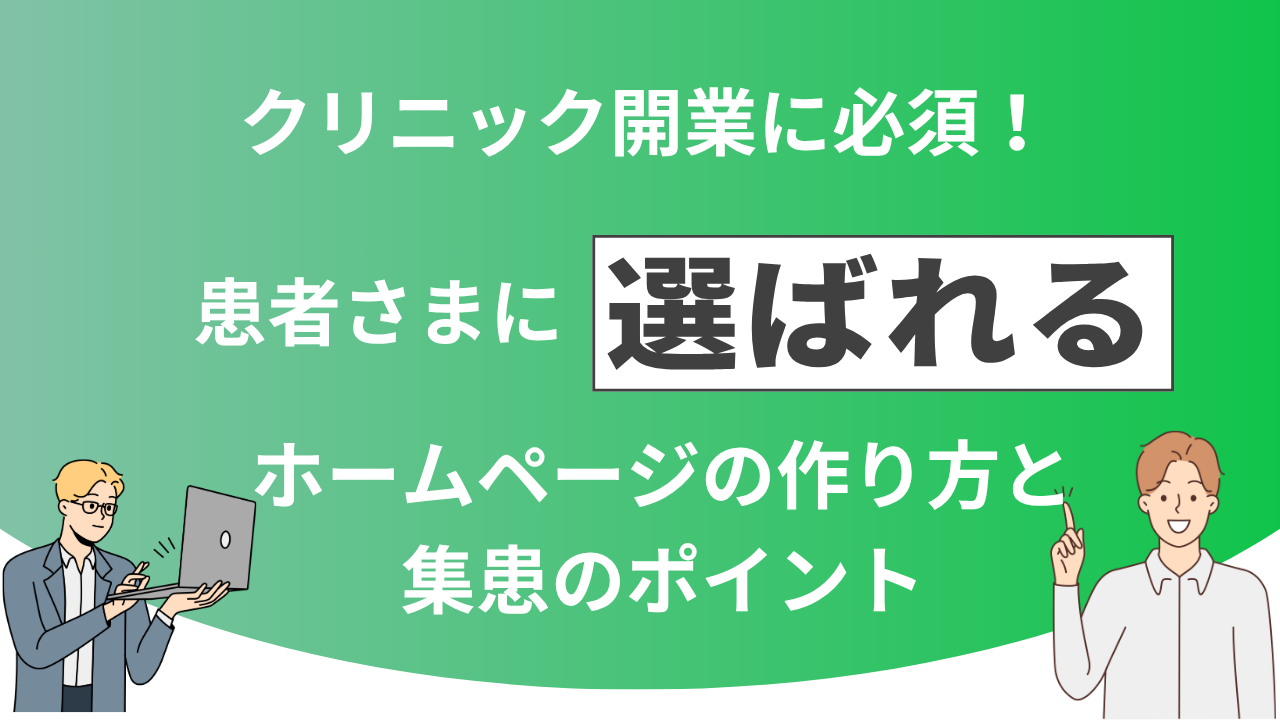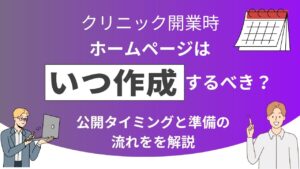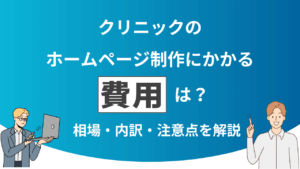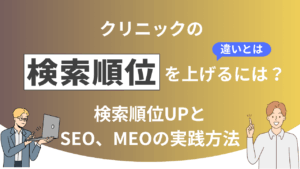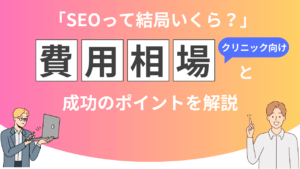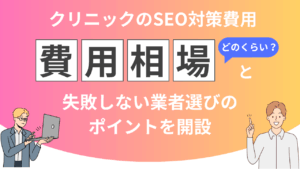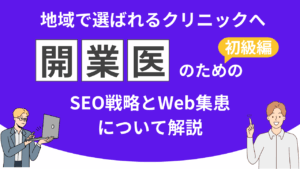はじめに|開業準備で“最初に見られる場所”はどこか?
クリニック開業に向けて、物件や内装、スタッフ採用などさまざまな準備を進める中で、見落とされがちなのが「ホームページ(HP)の重要性」です。
いまや患者さんの多くが、来院前にWebでクリニックの情報を調べてから判断しています。実際、「〇〇駅 内科」「△△市 皮膚科」などで検索し、検索結果やマップで出てきたクリニックのHPを確認する──という行動が、ごく一般的になっています。
つまり、ホームページは“開業と同時に最も見られる場所”であり、初診患者との最初の接点なのです。どんなに立地や診療内容に自信があっても、HPでの情報発信や見せ方によって“選ばれるかどうか”が大きく左右されます。
そのため、開業と同時にスタートダッシュを切るには、集患に強いHP制作とSEO対策がセットで必要不可欠です。
本記事では、クリニック開業時におけるHP制作のポイント、SEOとの連携方法、そして患者さんに「安心して選んでもらうための設計」について詳しく解説します。

株式会社パドルシップ 代表取締役
京都大学卒、京都大学大学院修了
総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。
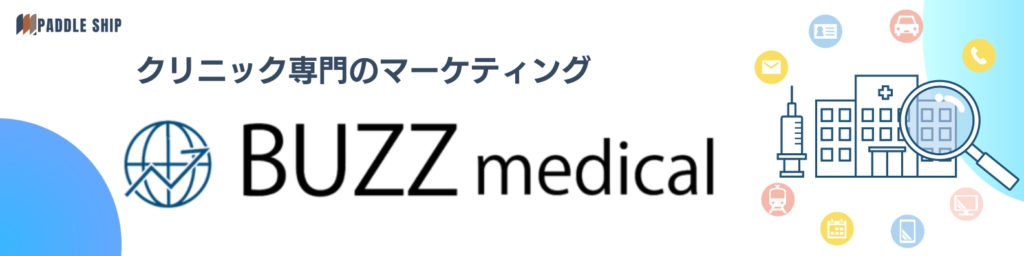
なぜクリニック開業時にホームページ制作が重要なのか?
理由①:開業初期の認知獲得に直結する
開業直後はまだ「どんなクリニックができたか」が地域に知られていません。検索結果に自院の情報が出てこない状態では、競合に埋もれてしまいます。
逆に、検索エンジンに対応したHPを公開しておけば、検索結果に表示されやすくなり、「新しい医院が近所にできた」と気づいてもらえる可能性が格段に高まります。
理由②:Googleマップでの検索にもつながる
クリニックのホームページがあれば、Googleマップの検索結果とも連携できます。たとえば「○○駅 内科」と検索したときに、地図上に医院が表示されたり、クリックしたときにHPにアクセスできるようになったりします。
最近では、スマートフォンで「近くのクリニック」を探す人がとても多くなっているため、地図で見つけてもらえるようにすることも大切です。
理由③:あとから載せる“集患(SEO)記事”の受け皿になる
開業後に「発熱外来の案内」や「花粉症シーズンの受診のポイント」など、患者さんの検索に合わせた記事を追加していくと、検索からホームページに来てくれる人がどんどん増えていきます。
ただし、こうした記事の効果をしっかり発揮させるには、最初に作るホームページの作りが大事です。はじめから「記事を追加できる設計」にしておけば、あとで無駄なく集患力を伸ばしていけます。
まず整えるべき!開業時ホームページの基本構成とは?
クリニックを開業する際、ホームページ(HP)は「デジタル上の入口」として非常に重要です。初めての患者さんにとっては、クリニックのことを知る第一歩がホームページになるため、必要な情報がわかりやすく整理されていることが求められます。
ここでは、開業時に必ず押さえておきたいホームページの基本構成要素をご紹介します。
① トップページ:第一印象を決める「顔」
訪問者が最初に目にするページです。以下のような情報をわかりやすく載せましょう。
- 院名、診療科目、エリア(例:「○○市の内科・小児科クリニック」)
- 写真(外観・院内・院長写真など)
- 簡単なごあいさつ・理念(安心感を与える)
- お知らせ欄(臨時休診や最新情報)
② 診療案内ページ:どんな診療をしているかを明確に
どんな症状・疾患を診ているかを、患者さん目線でわかりやすく伝えるページです。
- 診療科ごとの説明(例:内科、小児科、皮膚科など)
- 代表的な症状の説明(例:「発熱・せき」「花粉症」「生活習慣病」など)
- よくある質問(例:「予防接種は予約制ですか?」)
③ 医師紹介ページ:安心感を生む「人柄」の見える化
誰が診てくれるのかがわかると、患者さんの不安が和らぎます。
- 医師の写真・プロフィール(経歴・資格など)
- 診療への想い(患者さんへのメッセージ)
- スタッフ紹介(チーム医療の安心感を演出)
④ アクセスページ:迷わず来院できるための導線設計
地図・住所・交通手段などを正確に掲載し、来院しやすさをサポートします。
- Googleマップの埋め込み(スマホからナビしやすい)
- 最寄駅・バス停からのアクセス方法
- 駐車場・駐輪場の有無
⑤ 診療時間・休診日ページ:基本情報の整理
診療時間の一覧表や、休診日の記載は必須です。
- 曜日ごとの診療時間
- 祝日・年末年始の対応
- 受付時間との違いがある場合はその記載も
⑥ お知らせ・新着情報:患者さんとの“更新された接点”
クリニックの日常や重要なお知らせを定期的に更新する欄です。
- 休診日や診療時間変更のお知らせ
- インフルエンザ予防接種の案内
- 新しい検査・診療開始のご案内
⑦ スマホ対応デザイン(レスポンシブ対応)
多くの患者さんはスマホで情報を検索・閲覧します。スマートフォンでも読みやすく、タップしやすいデザインになっているかはとても大切です。
⑧ SEOやMEOとの連携に備えた設計
記事を追加したり、Googleマップと連携したりする機能を最初から備えておくことで、後からの集患強化がスムーズになります。
⑨ お問い合わせ・予約導線の設置
初診・再診の予約や、問い合わせが簡単にできるようにすることで、機会損失を防ぎます。
- 電話番号をタップで発信できるようにする
- 予約システムと連携
- フォームでの問い合わせ
医療広告ガイドラインへの対応も重要
医療機関のHPは、厚生労働省の「医療広告ガイドライン」に準拠している必要があります。虚偽表示や誇大表現がないように、事実に基づいた適切な表現を行いましょう。
SEOに強いクリニックホームページを作る8つのポイント
ホームページは「作るだけ」では検索されません。検索結果の上位に表示され、多くの患者さんに“見つけてもらう”ためには、SEO(検索エンジン最適化)を意識した設計と運用が不可欠です。
ここでは、SEOに強いクリニックHPを作るために押さえておくべき具体的なポイントを整理します。
① 地域+診療科での検索に強くなる「キーワード設計」
患者さんは「○○駅 内科」「△△市 小児科」のように、地域名+診療科や症状で検索する傾向があります。
- 「どの地域から」「何の症状で」来院してもらいたいかを明確にする
- タイトル・見出し・本文中にキーワードを自然に含める
- 不自然に詰め込みすぎず、読みやすさとのバランスを保つ
例:
「◯◯市の生活習慣病なら|◯◯クリニック(内科・糖尿病内科)」など
② ユーザー目線で“わかりやすく、役に立つ”情報を掲載
検索エンジンは、実際に役立つコンテンツかどうかを評価します。
- 症状別に詳しく解説(例:「高血圧とは?」「発熱の原因と対処法」など)
- 来院のきっかけになる情報を丁寧に書く(例:「当院ではこう診療します」)
- 専門用語はかみ砕いた表現に
ポイント: Googleは“患者さんにとって信頼できる情報”を高く評価するため、医師による解説はSEO的にも有利です。
③ スマホでも快適に見られる「モバイル対応」
多くのユーザーはスマートフォンからクリニックのHPを見ます。スマホで見づらいサイトはSEOでも不利になります。
- レスポンシブデザインでスマホでも自動調整
- タップしやすいボタン設計
- 表や文章が画面からはみ出さないレイアウト
④ ページの読み込みスピードを最適化
読み込みに3秒以上かかるページは離脱率が高く、SEO評価も下がります。
- 画像のサイズを最適化(大きすぎる画像は避ける)
- 不要なスクリプトを入れない
- サーバーやCMSのパフォーマンスにも注意
⑤ 内部リンク構造を整理して、サイト全体の導線を明確に
検索エンジンはサイトの構造も評価しています。
- トップ → 診療案内 → 症状別ページ など、階層構造が明確に
- 各ページから他ページへ自然にリンク(例:高血圧のページから「生活習慣病の予防」へ)
- パンくずリスト(現在地のナビゲーション)をつける
⑥ 定期的な情報更新とSEO記事の追加
開業直後に作ったままでは、検索順位は下がってしまいます。新しいページや記事を追加することが、SEO評価の維持・向上に有効です。
- 院内のお知らせ、休診情報などの更新
- 健康情報や季節性疾患(インフルエンザ、花粉症など)の解説記事
- よくある質問(FAQ)の追加
⑦ Googleマップ(MEO)と連携したローカル対策
Googleマップでの検索結果に表示される「ローカルパック」に出るためにも、HPとの情報整合性が必要です。
- クリニック名、住所、電話番号(NAP情報)をHPとGoogleビジネスプロフィールで統一
- HP内にGoogleマップを埋め込む
- 「アクセス」ページをしっかり整備する
⑧ 医療広告ガイドラインに準拠した安全なSEO設計
医療分野の情報は特に厳しくチェックされます。
- 「必ず治る」などの断定的表現は避ける
- 医師監修の記載(名前や資格)を明示する
- 客観的な事実に基づく表現のみ使用
SEOに強いホームページとは、「検索に強い」だけでなく「患者さんに選ばれる」構成になっていることが大前提です。以下を意識してHPを制作するようにしましょう。
- 見つけてもらいやすくする設計(キーワード・構造・スピード)
- 見た人が「ここに行きたい」と思える内容(信頼・安心・便利さ)
- 継続的に育てていく“資産型コンテンツ”
パドルシップの支援事例と、安心して任せられる理由
パドルシップでは、医療機関に特化したWebマーケティング支援として「BUZZ Medical」サービスを提供しています。SEOやGoogle広告を単独で行うのではなく、ホームページ制作・MEO・コンテンツ戦略までを一貫して設計し、フェーズに応じた最適な集患戦略をご提案しています。
実際の支援事例:都市部郊外の内科クリニックでの成果
実際に、ある内科クリニック(郊外・駅から徒歩15分の立地)では、開業直後からWeb戦略を立案し、開業後半年以内に以下の施策を実施しました:
- 開業直後の段階で競合分析とSEOキーワード戦略を策定
- 同時に、Google広告のキャンペーンを設計し開業初期から配信開始
- ホームページ内に記事を10本以上掲載し、SEOのベースを構築
- その結果、開業4ヶ月以内にWeb経由の来院が全体の25%を占め、売上ベースで30〜50%の増加を実現しました。特に「◯◯駅 内科」「△△市 発熱外来」など、地域+症状を含むキーワードで検索順位上位を獲得したことが集患に直結しました。
このように、「広告の即効性」と「SEOの資産性」を組み合わせた戦略設計によって、立地に左右されない安定経営を実現した事例です。
安心して任せられる3つのポイント
① 医療広告ガイドライン準拠のWeb設計
医療広告は法律による表現の制限が多く、違反すると行政指導の対象となります。
パドルシップでは、厚生労働省「医療広告ガイドライン」に準拠した制作・運用を徹底しています。
- 医療法違反となる誇大表現(例:「必ず治る」など)を排除
- 第三者による口コミや症例紹介の適正な掲載方法に対応
- 医師名や実績に関する記載方法をルールに沿って整理
法律面のリスクを回避しながら、SEOやGoogle広告の効果も最大化できる構成を実現します。
② SEO・MEO・広告・制作まで一貫支援
パドルシップでは、SEO対策・Google広告・MEO(Googleマップ)・HP制作を“分断せず”に一体で提供できるため、以下のようなメリットがあります:
- 戦略がブレず、全施策が一貫して集患を目的に最適化される
- 担当窓口が一本化されるため、運用負担が少ない
- 各施策のデータを横断的に分析し、費用対効果を高めやすい
特に「Webに詳しくない」という開業医の方でも、すべて任せられる”丸投げ”体制で、信頼感のある支援を実現しています。
③ フェーズ別で無駄のない集患設計
開業前から開業後までのフェーズに応じて、適切な施策を段階的に切り替えていく戦略設計もパドルシップの強みです。
| フェーズ | 主な目的 | 提供施策例 |
| 開業前~直後 | 認知の獲得 | Google広告、MEO登録、LP制作・運用 |
| 開業半年以降 | 安定的な集患基盤構築 | SEO記事追加、構造改善、検索分析 |
| 安定期~次の拡張 | 費用対効果の最適化・更なる売上拡大 | 広告運用最適化、定期改善提案、ポータルサイト制作・運営 |
「今すぐ来てもらうための施策」と「将来に備えた施策」をバランス良く設計することで、長期的な集患体制を築いていきます。
まとめ|クリニックの開業準備は「見つけてもらう設計」から始める
クリニック開業の成功は、「良い診療をすれば患者さんが自然に集まる」という時代から、「どうやって見つけてもらうか」を考える時代へと変化しています。
いまや、患者さんの多くは「Googleで検索」や「Googleマップで調べる」ことでクリニックを探しています。開業初期からSEOやGoogle広告、MEOといった“検索に強い仕組み”を設計しておくことが、スムーズな認知拡大と来院につながる鍵になります。
特に以下のようなケースでは、開業前の段階から戦略的なWeb設計が不可欠です。
- 駅から距離がある、競合が多い立地
- 内科・小児科・皮膚科など検索ニーズの高い診療科
- 医療法人で複数院展開を見据えているケース
ホームページは「作れば終わり」ではなく、「検索され、見つけてもらい、信頼される」ためのスタート地点です。SEOを意識したページ構成、Google広告による初期露出、Googleマップと連携したMEO対策など、複数の施策をバランスよく組み合わせて、初めて効果的な集患ができます。
パドルシップでは、こうした「見つけてもらうための仕組みづくり」を、開業準備段階から一貫してご支援しています。開業前の相談だけでももちろん可能ですので、「Web集患に強いクリニックを目指したい」とお考えの方は、どうぞお気軽にご相談ください。