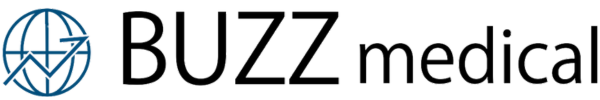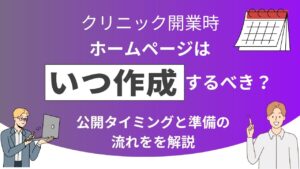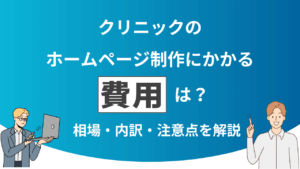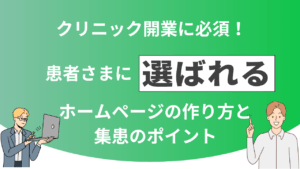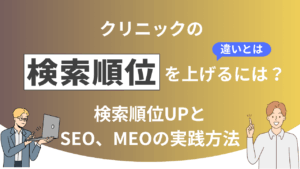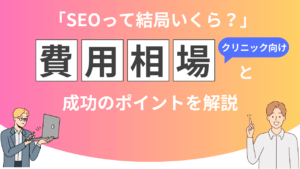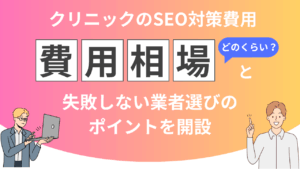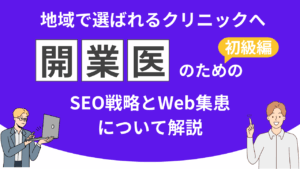はじめに
開業医として良質な医療を提供しつつ、自院の経営を安定させるためには「集患=患者さんに選ばれる仕組みづくり」が欠かせません。その中でも、近年主流となっているのが「Webを活用した集患対策」です。
ホームページを作るだけでは不十分で、「検索されたときに表示される」「見た人に来院してもらう」ための仕組みが重要です。そこで注目されているのが、SEO(検索エンジン最適化)とGoogle広告(検索連動型広告)です。
この2つはどちらも検索結果に関わる施策ですが、その仕組みや効果は大きく異なります。この記事では、クリニック経営者の視点から「SEOとGoogle広告の違い」「どちらを選ぶべきか」「併用の考え方」までをわかりやすく解説します。

株式会社パドルシップ 代表取締役
京都大学卒、京都大学大学院修了
総合電機の技術職、日系コンサルティング会社で新事業企画、ベンチャー支援等の経験を経て、2023年に株式会社パドルシップを設立。江戸川区のクリニック立上や戦略立案、集患を経験し、現在も経営に参画。
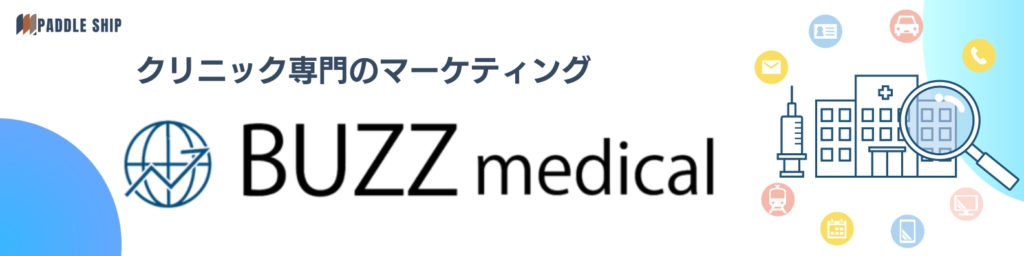
SEOとは?検索順位を高めて“自然に見つけてもらう”仕組み
SEO(Search Engine Optimization)とは、Googleなどの検索エンジンにおいて「○○駅 内科」「△△市 皮膚科」といったキーワードで検索されたときに、自然検索(広告以外)の上位に表示させるための取り組みです。
特徴:
- キーワード記事や内部構造を整えて順位を上げる
- 一度上位に表示されると、安定して流入を得られる
- 時間はかかるが、継続的に効果を発揮する“資産型”施策
SEOは即効性こそ低いものの、コンテンツが蓄積されればされるほど検索流入が強化され、広告費をかけずに安定した集患ができるのが最大のメリットです。
Google広告とは?即効性のある検索連動型広告
Google広告とは、Google広告などを通じて特定のキーワードに対して検索結果の上部(広告枠)に表示する広告手法です。たとえば「○○駅 内科」と検索した際、上部に“広告”と表示されているのがこの形式です。
特徴:
- クリック課金型:クリックされるたびに費用が発生
- 即日配信・即効性がある(開業直後に向いている)
- 配信を停止すれば流入もゼロになる
短期間で多くの患者さんに知ってもらいたい場合や、開業直後の集患には特に効果的です。一方で、中長期的に見ると広告費がかさむ傾向もあり、継続には費用対効果の見極めが必要です。
SEOとGoogle広告の違いを表で比較
SEOとGoogle広告は、どちらも検索エンジン上での「見つけてもらう」ことを目的としたWeb集患手法ですが、そのアプローチ・表示形式・効果の出方には明確な違いがあります。
ここでは、クリニック経営における施策選定の参考として、それぞれの特徴を項目ごとに比較表にまとめました。
| 比較項目 | SEO | Google広告 |
| 表示位置 | 自然検索の上位枠(オーガニック検索) | 検索結果の広告枠(ページ上部など) |
| 費用体系 | 月額固定・継続課金(成果報酬型もあり) | クリック課金(1クリックごとに費用発生) |
| 効果の出方 | 中長期的(3ヶ月〜) | 即効性あり(即日配信可能) |
| 資産性 | 高い(記事やページが資産になる) | なし(広告停止で流入ゼロ) |
| 向いているケース | 既存の検索流入強化・安定的な集患を目指す | 開業直後や短期的に集患したい場合 |
SEOは、一度検索上位に定着すれば“広告をかけなくても”継続的に流入を得られる可能性がある一方で、成果が出るまでに時間を要します。対して、Google広告は即時的に露出を得られる反面、広告を止めると即座に効果も失われる「短期的な手段」と言えます。
どちらが優れているというよりは、目的・予算・タイミングに応じて最適な使い方をすることが重要です。特に開業初期にはGoogle広告で認知を高めつつ、並行してSEOで中長期的な流入の基盤を作っていく戦略が効果的とされています。
どちらを選ぶべき?理想は“使い分け”と“併用”
SEOとGoogle広告は、それぞれ強みと弱みが異なるため、クリニックの経営フェーズや集患目標に応じて“使い分け”ることが重要です。そして、より効果的に集患成果を上げたい場合は、両者を“併用”する戦略が理想的です。
開業初期(〜半年)はGoogle広告が有効
開業したばかりの時期は、ホームページも検索エンジンからの評価がまだ高くなく、SEOの効果が出るまで時間がかかります。この段階では、「まず知ってもらう」ことが最優先となるため、Google広告によって即座に検索結果上部へ表示されることが大きなアドバンテージになります。
広告によってWeb上での露出を増やし、アクセスを増やすことで、クリニックの存在を早期に地域住民に伝えることができます。
安定経営フェーズではSEOが主軸に
一方で、開業から半年〜1年が経過し、ある程度の認知と来院数が確保できてきた段階では、Google広告だけに依存する集患はコスト負担が重くなってくる可能性があります。
ここからは、自然検索からの流入を安定的に得るための「SEOコンテンツ」の育成が重要となります。SEOは一度上位表示されれば長期間にわたって患者との接点を維持でき、広告費をかけずに流入を得られる“集患基盤”として機能するため、長期的なコスト効率に優れています。
なぜ併用が効果的か?
実際には、「広告」と「SEO」は別々のものではなく、患者の検索行動全体をカバーするための両輪と考えるべきです。患者さんの多くは以下のようなステップを踏んで情報収集を行います。
- 症状や診療科で検索(→広告やSEOに表示)
- 上位に出たサイトをいくつかクリック(→広告または自然検索)
- ホームページを確認し、信頼できそうかを判断
- アクセス・診療時間・口コミなどをチェック
- 来院を決定
この流れの中で、広告は認知の起点、SEOは検討段階での比較対象として活躍することが多く、両方が揃って初めてスムーズな来院導線が整います。
パドルシップの支援例
- 開業0〜6ヶ月: Google広告を中心に短期集患 → 同時にSEO記事を育て始める
- 開業6ヶ月〜1年: SEOコンテンツが徐々に評価され始める → 広告の費用対効果を見極めて調整
- 1年以降: SEOによる自然流入を基盤にし、必要に応じて広告を補助的に活用
このように、段階的に施策を移行・併用していくことで、コストと成果のバランスを最適化しながら、継続的な集患体制を構築することが可能です。
パドルシップによる支援実績と安心体制
パドルシップでは、医療機関に特化したWebマーケティング支援として「BUZZ Medical」サービスを提供しています。SEOやGoogle広告を単独で行うのではなく、ホームページ制作・MEO・コンテンツ戦略までを一貫して設計し、フェーズに応じた最適な集患戦略をご提案しています。
実績例:駅からやや離れた内科クリニックでの成果
実際に、ある内科クリニック(郊外・駅から徒歩15分の立地)では、開業直後からWeb戦略を立案し、開業後半年以内に以下の施策を実施しました:
- 開業直後の段階で競合分析とSEOキーワード戦略を策定
- 同時に、Google広告のキャンペーンを設計し開業初期から配信開始
- ホームページ内に記事を10本以上掲載し、SEOのベースを構築
その結果、開業4ヶ月以内にWeb経由の来院が全体の25%を占め、売上ベースで30〜50%の増加を実現しました。特に「◯◯駅 内科」「△△市 発熱外来」など、地域+症状を含むキーワードで検索順位上位を獲得したことが集患に直結しました。
法令順守と品質管理
また、パドルシップでは厚生労働省の「医療広告ガイドライン」や医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書に完全準拠し、以下のポイントを遵守しています。
- 客観的事実に基づいた表現(医師の実績・診療内容などの記載方法)
- 誤認を与える可能性のある表現の排除(過度な効果表現やNo.1表記など)
- 実績紹介や口コミ掲載時のルールの順守(第三者評価と引用の明示)
このように、法的リスクを回避しながら、最大限効果を発揮する表現・構成を実現している点も、安心して任せていただけるポイントの一つです。
まとめ|“今すぐ”と“将来”を見据えた施策選びを
SEOとGoogle広告は、「検索結果で見つけてもらう」という点では同じですが、その仕組みも使いどころも大きく異なります。
- 広告:即効性で「今すぐ」の認知獲得に
- SEO:継続的なコンテンツ育成で「将来」の資産に
開業フェーズ・立地条件・集患目標に合わせて最適な施策を選び、必要であればプロと相談しながら、中長期で“選ばれるクリニック”を目指す戦略を立てていきましょう。